だいもんじやま(466m)
山歩記 INDEX へ

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都市の東山にある如意ヶ嶽(にょいがだけ)472mの支峰(西峰)が大文字山
銀閣寺バス停(9:55)→行者の森石碑(10:10)→火床最上部(10:50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行者の森石碑前を右へ、10分程歩いて右側にある小さな橋を渡る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
 
京都五山の送り火は京都四大行事の一つ。「大文字」大文字山(如意ヶ嶽)・ 「妙」松ヶ崎西山「法」松ヶ崎東山・「舟形万灯籠」西加茂船山・「左大文字」北区大北山 「鳥居形松明」嵯峨鳥居本曼荼羅山。五山で炎が上がりお精霊(しょらい)さんと呼ばれる 死者の霊をあの世へ送り届けるとされる。いつか送り火そのものを見てみたいと思う  
本来は一山一文字らしいが西山と東山をあわせて妙法山と呼ぶこともある この日は天気は良いものの霞んでいたので「舟形万灯籠」が肉眼では微かに見えた けれどカメラでとらえる事は出来なかった。「鳥居形松明」は全く分からなかった。  
伸びているので山頂は別にあるのではと思って行ってみることにした。 踏み跡はしっかりしているけれど山頂らしき所は見つからず、一人で心細 かったので途中で引き返した。しかし引き返している時に同じように山頂 を探している2組に出会い再度探しに行くことにした  
 
菱形基線(りょうけいきせん)とは地表の歪み(地殻変動)を知るために設置されたもの、 4つの測点を結んだその形から菱形基線測点(りょうけいきせんそくてん)と呼ばれるよう になったそうです。天測点と良く似ていますが測量の目的が違うようです  
 
 
かなり遠かったのでズームアップ(ブレブレ) 右)中尾城址  
きゅうり漬けを買って食べる、キュウリは丸ごとかじるに限る  
 
 
琵琶湖疎水の分線が南禅寺境内を通過するため周辺の景観に配慮して 田辺朔郎が設計して1888年(明治21年)に完成した  
琵琶湖疎水とは琵琶湖の湖水を京都市へ流すために作られた水路  
 
 
 
 
 
 

日本最古のエレベーターがあって今も動いている
この後、観光客を掻き分けながら河原町を通って四条室町の |
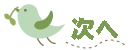



 岩山
岩山