ごしょがたけ(246.9m)うまがたけ(216m)
山歩記 INDEX へ
 |
|
| 御所ヶ谷神籠石 2021年12月 福岡県
福岡県行橋市にある御所ヶ岳と馬ヶ岳に登った。 活動時間:4:30 距離:7㎞ 累積高低差:上り454m/下り457m |
|

 |
|
| 第一駐車場にある 案内板 |
第三駐車場があって 此処が登山口となる |
| トイレのある第一駐車場に車を停めて10分程歩いた所に第三駐車場はある | |

 |
|
| 八十八箇所めぐりの札所 | ヒモヅルの群生地を通る |
| ヒモヅルは本来は熱帯性のシダ植物、九州と本州の一部で確認 されていて環境省の絶滅危惧種に指定されている極めて貴重な植物 |
|

 |
|
| 中門跡の石塁 御所ヶ谷の神籠石(こうごいし) | |

 |
|
| 排水口が設けられている | 八十八箇所めぐりの 札所である野仏が点在する |

 |
|
| 山城らしい景観 | 景行神社 |

 |
|
| 礎石建物跡 | 奥ノ院へ向かう |

 |
|
| 石仏 | 奥ノ院 |

 |
|
| 向こうに見えるのは 馬ヶ岳 |
ヤブツバキ |

 |
|

 |
|
| 遠くに英彦山方面の展望 | 溜池が沢山ある |

 |
|
| シダが生い茂る | 御所ヶ岳山頂 三等三角点 点名:木山 |
 |
|
| 山頂から馬ヶ岳本丸跡と二ノ丸跡が見える | |

 |
|
| 航空自衛隊 築城基地方面 |
求菩提山方面) |
| 御所ヶ岳山頂で展望を楽しみながらのランチの後、馬ヶ岳に向かいます | |

 |
|
| 急な下り ロープではなく ゴムホースが設置されていた |
御所ヶ岳は別名ホトギ山 |

 |
|
| 土塁の上を 歩くような感じ |
馬が岳本丸跡に到着 |

 |
|
| 新田氏表忠碑 | 遠くにうっすらと 英彦山と鷹ノ巣山 |
|
馬ヶ岳城は天慶5年(942)源経基が築いたと伝えられ 新田氏など歴代城主の伝承が残されていますが歴史を 辿れる確かな記録は室町時代の応永12年(1405)から |
|

 |
|
| 二ノ丸跡に到着 四等三角点 点名:六部岩 |
福智山方面 |

 |
|
| 京都平野の展望図 | 平尾台、貫山方面 |
 |
|
| 貫神の祠の向こうに貫山 | |

 |
|
|
本丸跡よりも二ノ丸跡の方が見晴らしが良い 京都平野を一望でき、周防灘も見える |
|

 |
|
| 大谷登山口に向けて下山開始 | |

 |
|
|
途中、展望所に寄り道すると太閤岩、官兵衛岩、又兵衛岩 など馬ヶ岳城ゆかりの人物の名を付けた岩があった |
|

 |
|
| 展望所から二ノ丸跡と 本丸跡が見える |
登山道へ戻る |

 |
|
| 土塁状の尾根を歩く | 大谷登山口に到着 |
| 此処から今朝、車を停めた第一駐車場まで舗装道路を歩いて行く | |

 |
|
| センリョウ | 堀切 |
| 堀切とは山の尾根を堀で切断して攻めにくくしたもの | |

 |
|
| 馬ヶ岳が見える所に 史跡馬ヶ岳の石柱 |
大島八幡神社の銅製の鳥居 |

 |
|
| 子連れ狛犬 | 帰りの車の中から 馬ヶ岳を振り返る |
 |
|
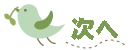



 岩山
岩山