いいださん(431m)
山歩記 INDEX へ
 |
|
| 身近な里山 飯田山(熊本百名山) 2020年12月 熊本県
飯田山は熊本平野の北東部に位置する山。昔話によると熊本平野を 今日は公共交通機関を使って麓迄行き、10数年振りに飯田山に登ることにした |
|
  |
|
|
県道232号線沿いの小池三差路バス停でバスを降り交差点を左折、 国道443号線を北へ、木山からの路線バスの「下砥川飯田山登山口」 バス停の先から右折する。田園風景を左右に見ながら暫く歩く |
|
  |
|
| 暫く行くと案内板があった。車は左へ、登山者は直進 | |

 |
|
| 田んぼのあぜ道に ホトケノザ |
霜が融けて水滴が キラキラ輝いて見える |

 |
|
| 舗装道路の脇に 唐突に三角点が・・ |
民家の庭先には サザンカが咲いている |

 |
|
| 林道っぽくなってきた | 金峰山との背比べで 負けた時にこぼれた水で 出来たとされる新屋敷池 |


|
|
|
一丁石仏 常楽寺迄の参道には、この新屋敷から一丁(約109m)毎に 石仏が安置されており、一丁から十四丁までの里程となっている。 江戸時代中期に建立された石仏は明治初期の廃仏毀釈によって破壊されたり、 長年の風雨により損傷が激しく、平成になって新たに石仏が建立された |
|


|
|
| 江戸時代からの 古い石仏 6体ほど残っている |
歩行者専用 車は通れない |


|
|
| 11丁石仏 阿閦如来 |
シマカンギク |
| 「あしゅくにょらい」物事に動じず、迷いに打ち勝つ強い心を授ける仏 | |


|
|
| よめご坂 斜め右上に登って行く |
「飯田山登山口」 此処に来てやっと登山口とは・・・ |


|
|
| 水子地蔵 | 常楽寺に到着 |
 |
|
| 紅葉真っ盛りの見事なカエデ 常楽寺の山門につづく石段は「乱れ積法」でとても珍しい |
|
 |
|
| 天台宗大聖院 常楽寺の山門 山号は飯田山 | |


|
|
| 金剛力士像 吽形(左) 阿形(右) | |


|
|
| 本堂 | 鐘突き堂 |
 |
|
| 平安時代末期に創建された「天台宗大聖院 常楽寺」の本堂 天台・真言・浄土宗に禅宗を加えた四宗の学問と 修行の道場としての性格を持つ寺院だった |
|


|
|
| 雰囲気のある石燈籠 | 本堂の横から 山道に入って行く |


|
|
| やっと山道らしい土の上を歩ける | |


|
|
| 常楽寺から 此処に出てきた |
林道を少し歩き 直ぐ左の男坂へ |


|
|
| 山道を歩けて嬉しい | 山道は呆気なく終わり 白山神社に突き当たる |


|
|
| 神社の右へ 展望休憩所 |
山頂は広い自然公園に なっていた |


|
|
| 飯田山山頂標識と 一等三角点 |
眺望案内 |
 |
|
| 熊本平野を一望する眺望案内 | |


|
|
| ベンチも沢山ある | 何時もの散歩コース 江津湖も見える |
 |
|
| 熊本市街地 今日は天気は良いのに霞んでいてハッキリ見えない 向こうに見える山が飯田山と背比べをして勝った金峰山(左) |
|


|
|
| 東側の展望は 僅かに脊梁の山が 見えるのみ |
石のテーブル兼 ベンチで賞味期限が 迫った「ぜんざい」 を作って食べる |
| 山頂で1時間ほど一人山カフェを楽しんだら下山します | |


|
|
|
清楚な白いサザンカの花とハナミョウガの実 往路を下山です |
|


|
|
| 十三丁 虚空蔵菩薩 |
県道脇のカラスウリ |
|
飯田山から下山して帰りのバスの時刻まで1時間半もあるので このまま自宅まで歩いて帰ることにした |
|


|
|
| 心なしか空気が 澄んで金峰山も 綺麗に見える |
木山川の堤防を歩く |


|
|
| 河原に下りる 階段をベンチ代わりに コーヒーブレイク |
田んぼを耕す 耕運機の周りに 鳥たちが集まって来る |
 |
|
| ケイトウの花と先程登った飯田山 | |


|
|
| アキノノゲシ | 今にも飛び立とう とするワタゲ |
 |
|
| 田んぼに下りて飯田山を振り返る | |


|
|
| 木山川の向こうに飯田山 | 秋津川の向こうに うっすらと阿蘇の山々 |
| 結局自宅までテクテク歩いて帰って来ました 活動時間:6時間40分 距離:15Km 累計高低差:上り482m下り477m |
|
|
一丁石仏 一覧 |
|
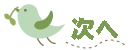



 岩山
岩山