わかくさやま(341.6m)
山歩記 INDEX へ
 |
|
| 世界遺産 春日山原始林の石碑 2022年4月 奈良県
御蓋山、東の花山、芳山も含め春日大社背後の山を総称して春日山という
破石バス停(7:45)→滝坂入口(8:20)→朝日観音(8:50)→首切地蔵(9:00)
活動時間:6時間40分(休憩含む)活動距離:15㎞ 累積高低差:上り797m/下り758m
|
|

 |
|
| 破石町バス停から 静かな通りを歩き始める |
新薬師寺に寄り道したけれど 朝早い為、閉まっていた |

 |
|
| 間違って春日山遊歩道へ 入ってしまい途中で引き返す |
東海自然歩道の 滝坂の道へ向かう |

 |
|
|
滝坂の道は春日山と高円山の間の谷川沿いに奈良の町と柳生を結ぶ 近道として開かれた道で柳生街道とも呼ばれる |
|

 |
|
| 妙見宮 五丁 | 江戸時代初期、当時の 奈良奉行が作らせたという 石だたみの道 |

 |
|

 |
|

 |
|
| 岩清水が滴り落ちる | 苔類も多い |

 |
|
| この辺りで谷川から離れる | |
 |
|
| 朝日観音 早朝高円山の頂からさしのぼる朝日に真っ先に照らされてる ことから名づけられたもので、実際には観音ではなく中央は弥勒仏、 左右は地蔵仏。文永2年(西暦1265年)鎌倉時代の石彫の代表的なもの |
|

 |
|
| ヤブツバキ | 首切り地蔵 |
| 荒木又右衛門がためし斬りしたと伝えられる首切地蔵 彫刻の手法から鎌倉時代の作と思われる |
|

 |
|
| 地獄谷園地 ベンチで一休み |
葉が肉厚な感じの スミレ |

 |
|
| カワウと新池 | 地獄谷石窟仏に向かう |

 |
|
| ドライブウェイを横切った所に地獄谷石窟仏の案内板がある | |

 |
|
| 地獄谷石窟仏の先は 危険らしい |
最初間違って反対方向へ行き 引き返し正規のルートへ |

 |
|
| 石窟仏はもう直ぐ | 史跡 地獄谷石窟仏 厳重に守られている |
 |
|
| 凝灰岩層をくり抜いた石窟で側面に仏像が線刻されている 聖(ひじり)が住んでいたという伝承があり聖人窟とも呼ばれる 年代:奈良時代(不詳) 左)薬師如来 中)廬舎那仏 右)十一面観音像 |
|

 |
|
| 廬舎那仏は弥勒仏 という各諸説がある 今も彩色などが残っている |
新池に戻り 春日山石窟仏へ |

 |
|

 |
|
| 史跡 春日山石窟仏 年代:平安末期久寿二年(西暦1155年) 東西二つの凝灰岩質の石窟からなる。石仏は全部で18体あり 地蔵尊を中心にしたものと大日如来と阿弥陀如来を中心にしたものに分かれる |
|

 |
|
| 春日山原始林は国の天然記念物になっている 杉の巨木などが多い | |
 |
|
| 世界遺産春日山原始林の石碑と朱塗りの大原橋 手前に大原橋休憩舎があるので此処で昼食をとる |
|

 |
|
| 鶯ノ滝に行って見る | リスが飛び出してきたけど 写真は撮れなかった |

 |
|
| 黒光りしている きのこ |
鶯ノ滝に到着 |

 |
|
| 水量はそれほどでもない | |

 |
|
| ルリセンチコガネ フンコロガシの仲間 |
水辺の植物が色々 |

 |
|
| 春日山最大の山桜 上部の方に少しだけ花が残っていた | |

 |
|
| 鎌研交番所 | 若草山へ |

 |
|
| 史跡 鶯塚古墳 若草山の頂上に築造された前方後円墳 全長103m 前方部幅30m 後円部径60m 清少納言の「枕草子」に記されている「うぐいすの陵」にあたるといわれる |
|

 |
|
| 鶯陵の石碑がある若草山山頂 三等三角点 点名:三笠山 標高341.65m |
|

 |
|
| 生駒山方面の展望 | 若草山三重目 古都奈良の町を見下ろす 金剛山や葛城山等の展望が良い |
| 若草山は別名三笠山とも呼ばれるように、三つの笠を重ねたような山容をしており 手前から一重目、二重目、三重目と呼ばれる3つの頂がある |
|

 |
|
| 桜の向こうに 御蓋山(みかさやま) |
八重の桜 |

 |
|
| 春日山遊歩道を歩く | 御蓋山に続く道 禁足地 |

 |
|
| トウゴクサバノオ | サワハコベ |

 |
|
| 遊歩道に沿って 谷川が流れる |
春日山遊歩道は此処迄 |

 |
|
| 茶店 | 一言主神社 |

 |
|
| 中門・御廊 (ちゅうもん・おろう) |
|

 |
|
| 御蓋山浮雲峰遥拝所 | 幣殿・舞殿 (へいでん・ぶでん) |

 |
|

 |
|

 |
|
| 中央に見えるのが 御蓋山(みかさやま) |
飛火野 |
 |
|
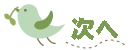



 岩山
岩山