おおだいがはら(1,695m)
山歩記 INDEX へ

|
2015年5月 三重県・奈良県 日本有数の多雨地帯、三重県と奈良県の県境に位置する大台ケ原。昭和34年の伊勢湾台風による大量の風倒木搬出を契機に苔の衰退→ミヤコザサの繁茂→笹類を食べる鹿の繁殖→鹿による草木の食害等々色んな要因で森林の衰退が加速したと言われている。大台ケ原は大きくは東大台と西大台とに分かれる。西大台は自然保護の為入山規制があり、許可を得ないと立ち入ることは出来ない、今日は自由に立ち入ることが出来る東大台の人気のハイキングコースをゆっくりと自然観察気分で歩く。
ビジターセンター → 日出ヶ岳 → 正木ヶ原 → |
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|

|
 
|

|

|

|
 
|
 
|
 
|

|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
右)アケボノツツジの花も九州の花より少し小さく感じる |
 
|

|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
殆どの花が九州のものと比べると小さい、九州の花はおおらかに育っている。栄養状態が良いようだ。 |

|
 
|
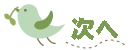



 岩山
岩山