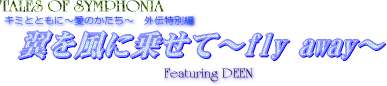
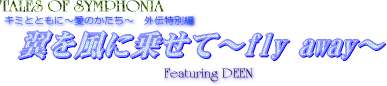
Episode.1
マリウス国王が突然、第一王女ヒルダに譲位の叡慮をお示しになられてから四ヶ月。蓬莱の頂に冠する白雪もようやくその紐を解き始める春が、今年もまたミズホの地に息吹の風を運んでくる。
藤林保豊(ふじばやし・やすとよ)。通称・イガグリ老は、自身久方ぶりに、ミズホ伝来の祭儀である啓蟄の儀を取り仕切っていた。
「やはり、ミズホの春はこれより始まるのじゃのう」
ミズホの民が主流とする農耕・木工。祀神の加護を受けた神木の鍬で、男たちが冬の間凍り付いていた田畑に鍬入れをする。そして、女は鍬入れされた土に祈りを込めながら、種付けをしてゆく。
儀式の後は、三日にわたる祭典となる。今年一年の繁栄と豊作を願いながら、唄い、舞う。
対外にひどく恐れられた情報網、謀略の尖兵であるミズホの民達の素顔は、実は自然を愛し、祭りを好む穏やかな人々であったのだ。
「頭領がお目覚めになり、今年の啓蟄は特に皆、喜びに満ちてますな」
藤林保興(ふじばやし・やすおき)。通称・太賀(タイガ)と言う、ミズホの副首領。保豊の女婿であり、保豊がさる事件で一時期昏睡状態にあった時、代理としてミズホを良く導いた有能の士である。
「陛下御退位の報にあって浮かれておる場合ではないのだがな。まあ……此度ばかりは許して下さるじゃろう」
太賀の盃を受ける保豊。大吟醸・和誉に代表されるミズホの酒は、五臓六腑に染み入る旨い地酒だ。特に祭りの日に傾けるこの一献はまた格別。
「いやはや。今年は特に賑やかでありますしな。某も嬉しゅうござる」
太賀もまた、実に心地よい気分で御酒に与っていた。
「おお、そう言えばあのお二方はいずれにある。是非、一献」
「どうやら、輪舞にあるようです」
春宵に映えるシルヴァラントを照らす炬火と舞踊を誘う雅楽。民らは神を楽しませ、共に語らい、共に酔わんがために踊り、舞う。戯謔に溢れているようで実は厳かな祭典。しかし、そんな輪舞の中に、極めて異質な姿がある。
「あーんっ、上手く踊れないですわ。お兄さまあ!」
ミズホの民族衣装、『キモノ』を身に纏った橙のショートヘアの美少女が、その小柄な体躯にだぶだぶの袖口を鬱陶しげに摘みながら、傍らで踊る紅髪の美青年に縋っていた。
「ははは……それ、セレスにゃやっぱ大きすぎたみてえだな」
と言いながら、くるりと背後を振り返り笑う。
「な、何さゼロス。あ、あたしの所為だって言うのかい?」
美麗な黒髪を束ねた美女が、その白い頬をほんのりと赤く染めて膨らませながら、ゼロスを睨んでいる。
「そんなこと言ったって、俺達のキモノ見繕ったのは、しいなじゃねえか。ん――――まあ、俺は何を着たってピッタシなんだけどな。さすがにセレスは――――」
「むぅ……ヒドイですわお兄さま。それは私が“何を着ても似合わない”と仰有っているのですか」
ふくれたセレス、きゅっとゼロスの腕を抓った。
「あいてててっ! 違、違うってばよ。いやな、お前もどう見たってそれ、突っ込む余地ありすぎだろ」
ずるずると引きずる裾。それはセレスの子供から逾(いよいよ)大人へと変わる絶妙なスタイルを全く介し表さない、寸胴。
「似合う似合わねえ以前の問題だろが。なあしいなよ」
「……あはは」
誤魔化しの利かない状況にあっての誤魔化し笑い。
「ああ、ごめんねえ。やっぱりあんたには子供用が良かったかなあ」
キモノのことである。
「むっ……そ、そのようなことあるはずがありませんわっ! このくらい、こうして……」
何を思ったのか、セレスはだぶだぶの袖や裾をせっせとまくり上げる。不格好な裏生地の露出したキモノの裾。そこから伸びる白くか細い腕や脛が何故か可愛らしく見える。
茫然とこの美少女の仕種を見ていた兄としいな。
「努力は認めるがな……」
「はぁ――――――――」
仕事のやり終えたセレス。見せびらかすようにくるりと廻った。
「どう? お兄さま。これで完璧でございますでしょ?」
「ああ。ある意味完璧かもしれん」
健気な努力にゼロスはただ苦笑するしかない。
「そうだねぇ――――仕方ないか。……んーと、セレス。あんたにもっと良いキモノがあるんだよ。着てみる気ないかい?」
「えぇ。それはどういうことですの? この衣装はまだ完成されてはいなかったとでも。……ヒドイですわ、しいなさん。お兄さまの前で不完全な私をさらけ出してしまうなんて」
顔を赤くして怒るセレス。ミズホに来てから何度もセレスの忿怒を見たせいか、しいなはもう慣れた。
南洋修道院に軟禁されていた時代は徐々に遠離る記憶の中にあったが、セレスにとって、兄ゼロスとの関係は、因果なもの以上に兄を強く慕い続ける矛盾と葛藤に苛まれ続けた痛ましいものであった。更には虚弱体質にこよなく近い身体だ。弱ければリストカット等の自傷行為で過度になればそれこそ自らの命を絶ちかねない、極限の状態にあったのだ。
セレスに与えられた艱難辛苦を自ら乗り越え、今こうして兄と一緒に静かに過ごせる幸運を手に入れることが出来たのは、他ならぬセレスが兄を想い慕い続けられた精神力に他ならない。
それほど強く兄を想うセレスが、兄の前では完璧でありたいと願う。彼女が癇癪を起こすのは兄に絡む時に限っていた。その他はまあ名家ワイルダー家の令嬢らしく上品で、時々高飛車な言動を取るが、その実無邪気で優しい性格をしている。ミズホの民もすぐにセレスを受け入れてくれた。狭隘な人間関係や空間に押し込められていた彼女が初めて目にした自由な青空、大地、緑の薫り。それが逆に戸惑い、心を塞ぎかけた時、声を掛けてくれたミズホの優しい少年や少女たち。お陰で同年代の友達も増えつつあった。
ゼロスにとっても、テセアラの政情が不安定なことを理由にミズホに在しているのは決して無為なことではない。
セレスの癒しの場、そして何よりも、しいなが側にいること。
ゼロスはマナの神子として、ずっと流転の人生を歩んできた。
テセアラやシルヴァラントを震撼させた悲しき元凶が斃れ、神子という名の呪縛から解き放たれた今、彼にとっても、こうした穏やかな日々は生まれて初めてのことで、またかけ替えの出来ない、必要な時間に他ならない。
「まあいいじゃないか。きっとあんたに似合うから。完璧かどうかはしんないけどさ……。まあ、嫌なら別に良いんだけど」
「い、嫌とは申しておりませんわ。す、すぐに案内して下さいな、しいなさん」
素直じゃないセレスに苦笑のしいな。
「わりぃな、しいな」
こっそりと手を合わせるゼロスに、ウインクを返すしいな。
しいなにとっても、こんな時間はきっと初めてだっただろう。心穏やかな日々。何気ない事がとても愛おしく思えること。
そんな時間を求めるために、しいなも果てしない戦いの最中にあった。同じものを求め合う彼女とゼロスが、互いの進むべき道を見つけたとき、惹かれ合っていた自分の心を知った。それは決して偶然などではなかった。
ゼロスは人生の伴侶として漸く藤林しいなという娘に巡り会い、しいなもゼロス=ワイルダーという青年の存在の大きさを認識した。
特別な言葉や品物は要らない。認め合えたこと。大地を育むマナや、磁場のように、二人は自然のままに結ばれた。
後は、恋人同士として、夫婦の契りを交わすだけなのだ。
しかし、世の中というものはそうそう何事も上手くは行かない。何を成すにも、きっかけというものが必要である。料理を成すのに火は欠かせない。その火熾しがなかなか出来ないのだ。
輪舞は続いているが、しいなやセレスが一旦抜けた今、休息の好機であった。
静かに輪を抜け、保豊や太賀の元へ行く。
「おお、ゼロス殿。丁度良かった」
太賀が掌を拍ち、ゼロスを手招いた。ゼロスから保豊、太賀への挨拶もそこそこに、太賀は対面の若者を指す。
「貴殿こそ、よくご存知の筈だ」
「…………」
ゼロスは直垂を纏ったその若者を見遣った。見覚えのある青年。
「あ、私は――――」
「待て」
名乗り上げようとした青年を、ゼロスは制止する。
「こう見えても人の顔は忘れねえもんさ。思い出す……んーと……」
しばらく、ゼロスはその脳裏に収められている、女性9割8分の人名リストを検索。やがて、一致した結果が出たのか、にやりと笑い、わざとらしく感嘆する。
「王立研究院のカセイ。服部家成(はっとり・いえなり)クン」
「正解です、ゼロスさん」
ミズホ三頭領家の一、服部十蔵保忠の次男、三蔵家成。寛藏保峻(かんぞうやすとし)の弟。
ゼロスとは級友であり、これが正真正銘の切れ者と来たものである。本来ならば卒業後、ミズホに戻って主家を支えるべきはずだったのだが、家成は敢えて王立研究院に残り、史書の研究に没頭していた。無欲な性格の通り、実に恭謙で穏やかな人柄である。因みに、他人を諱で呼ばない風習があるミズホの民。家成が本来の通称である『三蔵』を名乗らないのは、名実共にミズホの血族から離別したことを意味している。諱を呼ばれるのは、ミズホの民にとっては、人前に裸のまま出で立つようなものだからだ。
まあ、それがゆえに在学時はゼロスに頻繁に揶揄された経験があり、家成の字をしてカセイ君と綽名された。
しいなとも勿論旧知の仲で、不思議なのは家成に対しては、この御転婆娘も妙に従順なところがある。
「久しぶり……というか君、王立研究院はどうしたよ。まさか職を辞して来た訳じゃねえだろ」
「細々とながらも宮仕えの身。暇無くして帰郷は致しませぬよ」
飄然と笑う家成。
「辞めたんだ」
「仕事が一段落したのですよ。……それに、重要な話がありました。ゼロスさんがミズホにいて下されて、助かります」
「“重要な話”はもう腹一杯だな。何かは知らねえが、俺抜きで決めちゃって下さいと言うことだよ」
茶化すゼロス。すると家成はふっと表情を素に戻してゼロスを見据える。
「ヒルダ様の後嗣について、アンドリュース閣下はセレス殿を最右翼と思し召しとか」
「…………何?」
思わず、ゼロスは訊き返していた。
「女王に大公の慣例なく、閣下はヒルダ様の後継に際し、遠戚のセレス殿に白羽の矢を立てられました」
家成の報にゼロスは思わず失笑した。
「ハッ、埓もねえ。恩赦と同時にセレスの皇籍を除いたのは誰でもねえ王家じゃねえか。何を今さら――――」
「しかし、後継が定まらぬまま踐祚の儀に至ることを政府としても懸念され――――」
家成の言葉を、ゼロスは強い嘆声で遮った。
「しちめんどくせえな。政はもう勘弁してくれ。王家の血族ならテセアラ中に五万と散在しているだろ。どうでもいいが、セレスを巻き込むのだけはやめてくれ」
政争に疲れ切った様子のゼロス。王家や政府の名を聞いただけでもどっと疲れが来るようだった。
「しばらく、ゼロス殿よ」
保豊が二人のやり取りを止める。
「兄として、そして何よりも運命に呑まれ続けた貴公ら兄妹の立場、痛いほどようわかる。……しかし、事はテセアラの存亡に関わること。セレス殿の意向を直接聞いてみても良いのではあるまいか」
その言葉に、ゼロスは唸った。
「あいつはワガママに見えて結構、責任感が強い性格だ。そんな話をしたら――――」
「ワガママで悪うございましたわね!」
不意にゼロスの背後から疳高い怒声が響いた。
「うわっ、な、何だよ……驚かすな」
振り向くと、今度はぴたりとしたサイズの矢絣のキモノを纏った勝ち気な妹が、相変わらずの様相で兄を見ていた。隣には着替えをさせたしいなが、ほっとしたような表情を浮かべている。
「よ、ようセレス。やっぱ似合ってんじゃねえか。だぶだぶのやつよか、何倍も可愛いぜ」
しかし苦笑するしかないゼロス。見え透いた世辞に、セレスは笑顔が続かない。
「ありがと、お兄さま。それじゃ、気を取り直して、私と踊っていただけますかしら」
「ああ、いいねえ。行こう、行こう」
その場から連れ出すようにゼロスは妹の手を掴む。
「んん……見慣れたはずなのに、違和感のある人間がいるねえ」
不意にしいながそう言うと、間を置かずに笑い声。
「敵いませんね、しいなさん」
すくと立ち上がった家成がしいなに握手を求めると、彼女は苦笑を湛えながら、おずおずと握手を受ける。
「家成――――アンタって、本当に都会臭が抜けない男だねえ」
その皮肉に、家成は更に笑って返す。
「波瀾の伝記に事欠かず貴女にとっては、家成は当に華冑の蛙ですか」
「良くわかんないよ。でも、あまりいい感じとは言えないんだろ」
「どうやら、心からの歓迎とはほど遠いもののようです」
「私も聞くよ。……でも、それって今日じゃなくても良いんだろう」
「まあ、あまり長閑にとまではいきませんけどね」
「国家の一大事……なんてもう慣れに慣れまくっているサ。家成には悪いけど、ちょっとやそっとじゃ驚かないからね」
しいなの語気に対し、家成は言葉を呑み込んでしまった。
「まあしいなよ。せっかく旧友が戻ってきたのだ。硬い表情をほぐし話でも弾ませなさい」
太賀の言葉に、しいなは頷いた。
輪舞の中では、いつしかセレスが兄をエスコートしていた。手を引かれ、戸惑う表情のゼロスが笑みを誘うのだった。
翌日。昼下がりから始まる祭典の間、里はいつものような静寂の中にある。
ミズホ総領・イガグリ老藤林保豊の館はいつもとは違って、そこはかとなく緊張感が漂っているように思える。
席にはそれぞれ、総領・藤林 保豊、総領代・“太賀”藤林 保興、ゼロス=ワイルダー、次期総領代・藤林 しいな、ミズホ幹部の服部 十蔵保忠、百地 勘太夫重保などの面々、そして王立研究院参事・服部 家成が控えていた。
「セレス殿には都合ありにて……」
「呼ぶまでもねえ」
最初から、ゼロスはこの場にセレスを呼ぶことを嫌った。保豊も得心した。
「ならば服部家成殿、王家の意向、改めて申し上げよ」
保興の言葉に、家成は大きく頷き、口上を述べた。
「ヒルダ様のご天意は、王制憲法の改定。すなわち、立憲君主制の確立に伴う、テセアラ・シルヴァラント共和制国家への展望にあります。すなわち、アーネスト・アンドリュース国務相を首班に、国民議会を設置。人間族・エルフ族・ハーフエルフ族などの議員をもって構成し、国家の運営を裁断する……」
ヒルダ女王の構想では、統合世界。すなわちテセアラ・シルヴァラント国の新体制は、上下両院をもって編成される国民議会。上院はマーテル教会や貴族・学会・労組系の有識者で編成。下院は各州区における国政選挙にて選出。王家を実質元首とするが、政府とは一線を画す形を取るという。
いまだ根強く残る種族身分格差を取り除くには、確かにヒルダ女王が提唱する政治体系が一番良いのかも知れないが、新たな問題はきっと出てくるのだろう。
「王家が提唱する国家体制はわかった。アンドリュース閣下の青写真大いに結構なことだ。だが、それとセレスの件をだぶらせられては困るな」
ゼロスが語気強く言う。
「あたしも基本的にはゼロスに同意見だよ。今になってセレスを皇籍に復して後継者にしようなんて、王家の虫の良さにはほとほと呆れさせられるよ」
しいなが憤懣の色を濃く滲ませて言い切る。
「言い方を変えれば――――つまりは、国王家が存続しながら、民主的政治に移行するのはいかがなものかと」
保豊の言葉に愕然とする太賀。
「滅多なことを、頭領。テセアラ王家は民の拠り所でございますれば考えられませぬ。ヒルダ様は女王。皇嗣はいずれにせよ定められなければなりますまい」
「だったら、手っ取り早いこと。ヒルダ姫に大公を迎えればいい。それで全てが収まるだろう」
「国是は安易に枉げられるものではない。女王に大公の慣例無き伝統は、テセアラ王家千年に亘って守られてきたこと。言うのは殊に易し」
テセアラがいずれ立憲君主制の共和国家になるのは時代の流れなのだ。そんなことをミズホの小さな館で言い合いしても始まらない。
いつしか、議題はゼロスの妹・セレス一色になっていた。
しかし、議論は小田原評定。いつまで経ってもセレスへの良い道筋が見えそうもない。
わかっていても、苛立ちが募る。この感覚が嫌だった。もう、一杯の苦悩。二度と味わいたくはなかった、運命の流転。
ゼロスは席を立とうと、タタミに手のひらを突く。随分と空気が悪くなっていた。ちらちらとゼロスの様子を窺っていたしいなも、ゼロスの様子を察知し、腰を上げようとした。
その時だった。
不意に障子戸がごとごとと音を立て、一条の青空の光が射す。
「家成、そこまで言うならば王の威を以て姫神子を連れ出せばよいだけの話」
若いが低音で良く透る声が、不毛の議場を一瞬に鎮める。しいなが瞬間、目を瞠り、振り向いた。
「く……くちなわ!」
覆面を外した素顔は実に精悍な美青年。しいなが思わず声を上げたこの青年こそ、“蛇(くちなわ)”百地守保。ミズホを離郷してから随分と経つ。
「おお、蛇か。よくぞ戻った」
太賀が声を上げると、蛇は恭しく跪く。
「守保、恥を忍んで参りました――――総領」
ミズホ無類のカゲの帰参を許さぬはずはなかった。蛇の足跡は既に淘汰されるに等しい。
「積もる話は後にゆるりと……。それよりも家成、なぜ姫神子を連れぬ。思惑を言え」
蛇が家成にすごむと、家成はふうとため息をついた。
「セレス殿はゼロス殿の御妹。さも人攫いの如き所業で王都に迎えるのには大いなる憚りがあり」
「それだけではないだろうが」
「これはしたり――――畏れ多くも王家の叡慮に無体な因縁をつけるか蛇殿」
すると蛇は失笑する。
「今さらそんなことはどうだっていいさ。……ただ、一つだけ言えることがある」
くるりと、彼はゼロスを見た。
「どうするかは、姫神子が決めることだ。神子とて、それは重々承知していると思うが」
「……ああ。あんたの言う通りだな。本来ならセレス自身が道を定めるべきことだろう。こればかりは、遁れようにも遁れられねえ運命なのかも知れない。……でもな、あいつをまた籠の中に押し込めちまうような道だけは選ばすわけにはいかねえんだよ」
「ようやく……自由になったんだからねえ」
しいながふうと息をつく。
「いずれにしろ避けられねえ運命なら俺にも覚悟の程はある。セレスにもきちんと話す。カセイ……いや、服部家成さんよ、少しばかり猶予をくれや」
ゼロスの言葉に、家成は瞳を伏せて了承した。
「ゼロス――――」
いささかいきり立ち気味のゼロスを、しいなは心配そうに見遣った。
「心配すんな。こればかりは俺自身の問題だ。お前らに心配は掛けねえよ」
しかしゼロスの瞳は、どこか哀しげに空を泳いでいた。
「…………」
柱の影に立つ少女が思いつめたような表情を浮かべていた。
「お兄さま……」
セレスは胸元に手を組み、切なげに瞳を閉じていた。障子越しに聞こえてくる会話はどれも聞くに辛い。兄の姿を捜して、ここに来ただけなのに……。