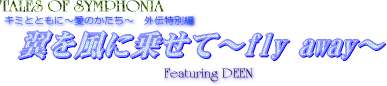
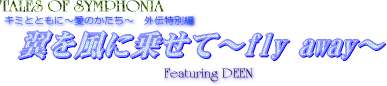
Episode.2
賑やかな祭典が終わると、途端に底知れぬ寂しさが世界を包む。まだ、明日もあると思っていても、やはり華やかな喧噪が落ち着くと、普段聞き慣れたはずの川のせせらぎや木々のざわめきも妙に愛おしく思うものだ。
今はもう無いが、かつて『救いの塔』と呼ばれた高塔がそびえ立っていた、ミズホ名霊峰・蓬莱。その連なる稜線からミズホの里にかけて、サクラと呼ばれる淡く美しい春の花樹が咲き誇るのだという。
その仄かで優しい香りが微風に乗り、里に伝わると、蓬莱の山脈が桜雲に霞むのが近い徴。
シルヴァラントの蒼い光に照らされた夜の山脈は、何とも表現のし難い幻想的な色合いに包まれる。
保豊や太賀から聞かされていたミズホの季節に、ゼロスはこの里が何故『神秘の里』と呼ばれているのか、解るような気がした。そして、どうしてもセレスに見せてやりたかった。これからは、ずっと一緒に居られるだろうと。
里の外れには、ミズホ独自の神を祀る社があり、その社から少し歩をずらせば、ちょっとした坂道が続き、ミズホの里を一眸できる小高い丘がある。
ゼロスは時々、この場所でぼうっと物思いに耽るのが好きだった。何となく、眼下に広がる優しい里から、上を向けば広大なテセアラの世界を望めるような気がする。
故郷・テセアラ。
なんだかんだと言っても、生まれ育ったこの世界を、ゼロスは憎しみ以上に、愛して止まないのだ。
やっと手にした、たった一人の肉親。妹セレスとの生活。やがて、しいなとともに家族を作ってゆくという夢に、ゼロスはらしくないと恥ずかしがりながらも前向きになっていたのだ。
「お兄さま?」
不意に声がした。驚くゼロス。振り返ると、どこかしか不安に沈んだように、力なき妹の愛らしい顔が、じっとゼロスを見つめている。
「……よーお、可愛い妹よ」
わざとらしく、投げやりに腕を振り上げる。
「お兄さまも……よくここに来られますの?」
ちょこんと、セレスは兄の傍らに腰を下ろす。
「良く来るぜ。お前も、良く来るのか」
こくんと、頷く。
「この場所――――私だけのとっておきの場所だと思っておりましたのに……お兄さまも知っていらしたなんて……」
はにかむセレス。ゼロスは手のひらにすっぽりと包んでしまうかと思うほど小さな妹の頭に手を当てると、優しくくしゃる。
「きゃ、やあ!」
そう言いながらも眼を細め、肩を窄めるセレス。
「さすが兄妹だな。考えることが似ているぜ」
「嫌ですの? お兄さま」
僅かばかり潤んだ眼差しを兄に向ける。ゼロスは口の端に苦笑を浮かべながら妹の髪の毛を指に絡ませ弄ぶと、優しくその額を小突いた。
「ばーか。そんなわけあるか。照れるけど、嬉しいんだよ」
どうしてだろうか。普段とは違って、ゼロスは素直な気持ちをありのまま口にすることが出来た。セレスは兄の言葉に少しばかり驚きながらも、にこりと微笑み、兄の腕に腕を絡めた。
「ここからの眺めは、最高ですわ……」
「――――ああ、全くだな。ん――――考えてみりゃ、お前とこうして夜の景色見るのは初めてか」
「あ――――そう言えば、そうですわね」
ミズホに来てからはずっと一緒にいたと思えた兄妹。しかし、振り返ってみればそれほどでもなかった。セレスが指折り数えて、小さなため息をつく。
「……ずっと、こうしていられれば良いなあ」
ゼロスの呟きに、セレスは驚いたように瞳を瞠った。
「お兄さま……?」
本当は何よりも嬉しい言葉。自分と同じ想いを兄も思ってくれている。不条理な運命に分断されていた絆の時間以上に、互いの存在を求め合える、言葉。
それなのに、セレスは驚いていた。あまりにも優しいゼロス。それは、そこはかとない寂しさに似た、慈しみの言葉に聞こえた。そして、それが自分が聞いた、重大な事象に全てが関わっていると言うことを、セレスには痛いほど伝わってきたから……。
「私も……そう、思いますわ」
躊躇い気味に、セレスはそう返していた。ゼロスはふうと小さく微笑むと、思いを巡らす。
中央の一使者である服部家成はともかく、ヒルダ女王の『叡慮』を蔑ろにしてはテセアラの人々を見捨てるに等しくなる。たとえ、アンドリュース国務大臣の指針にしても、それは同じだ。ゼロスが、それを選んだのだから。
「……うふふっ」
何を思ったのか、セレスは不意に兄の胴にしがみつき、か細い腕に目一杯力を込めた。
「セ、セレスっ?」
痛い感じには程遠い、こそばゆさ。しかし、セレスはまるで勝ち誇ったかのような表情で兄を見上げていた。
「いたたたっ、何すんだよっ」
「スキアリッ、ですわ」
きょとんとするゼロス。何処かしか幼気で哀しい笑顔に、ゼロスは胸が少しつまる思いがした。
「…………」
まっすぐ瞳を捉える兄の視線に、セレスは胸の奥底からふつふつと湧き上がってくる熱い感情に唇を噛みしめる。
そして、不格好に絡めた腕をおずおずと解くと、セレスは顔を伏せ、肩を窄める。
「セレス――――」
ゼロスが名を呼ぶと、セレスは不意を食らったかのように思わず瞳を上げた。その瞬間、柔らかな頬の肌が、突っ張られた。
愕然となるセレス。瞳には悪戯っぽく笑う兄の顔。突然の行動に、両手が空を彷徨う。
「ふに~~~~~~~~」
見慣れたふくれっ面が再現される。ゼロスは乾いた笑いを満面に浮かべ、戯けた。
心の余分な緊張感がすうと取れてゆくのを、ゼロスは感じた。妹は自分の思いに気づいているのかも知れない。それが、心を幾ばくか軽くさせた。
ぱちんっ……
指を離すと、セレスはいつものようにぶうと文句を垂れた後、ゼロスから身を離し、再び夜の静寂を俯瞰する。
しばらく、春の香を愉しむ虫の声と冬の名残を胸に吸い込む。そして、セレスは一つ、息を大きく吸った。
――――私……お兄さまの負担には、なりませんわ――――
その言葉に、ゼロスははっとした。
振り向けば、セレスは強い意志を秘めた微笑みを浮かべ、シルヴァラントを仰いでいる。
強く、それでもそこはかとない寂しさを秘めた、気が強く、可憐な少女。
ゼロスは常に思っている。身内を賛するわけではないが、セレスは絶世の美女になりうるだろう。それこそ、至上の座に登極されれば、国史に未来永劫、その美貌を称えられる女王となろう。
そう……女王となれば――――。
「なに、バカなこと――――言ってやがる」
そう返して、苦笑した。
再会と帰還の喜びもそこそこに、しいなと蛇、そして服部家成は芳しからざる様子でにらみ合っていた。
「何度も言うけど、ゼロスはそう簡単に折れないよ。それは分かっているんだよね、家成」
「言わずと知れたことです」
飄然と切り返す家成。
「姫神子は神子の意こそ第一。いかな王家の叡慮だとしても、引き離されれば姫神子は自らの命を絶つ」
「く、くちなわっ!」
さらりと過激な言葉を吐く蛇を慌てて制止しようとするしいな。
「あながち間違ってはいないだろう」
「そりゃ……そうだろうけどサ――――」
「軽挙妄動を戒めるのが、お前の役目だろうが」
蛇の強い口調に、しいなは戸惑う。
「それは――――。ああ、そんなに責めないでおくれよ……私だって、こう見えても色々と考えているんだ」
まごつくしいなに、蛇は失笑気味に顔を綻ばす。
「お前の生真面目さは相変わらずの様だな。……まあ、あんまり気負いすぎると調子崩しちまうぜ」
「…………」
過熱気味の精神を心地よく冷ますような蛇の口調。真実の和解以来、彼の本当の優しい部分が、具ににじみ出てきている。
「それはそうと――――まあ、俺が言えた義理じゃないが、家成。貴様、いつから国務相の尖兵に成り下がった」
突然、蛇の矛先が家成に向けられ、間髪入れずに口撃を始める。
「尖兵とはしたり。これは王家の冀望。私はその旨を伝えに来たに過ぎない。他意はありません」
沈着な家成の語気が若干強くなる。
「まあ――――いずれにせよ、国務相に伝えた方が良いぞ。礼を尽くさずして蒼生の芽は息吹かぬと。御旗を立て統合世界を遍く治める気概あるならば、まずは誠意を示して見せよと」
蛇の言葉に、家成は押し黙る。
重々しい沈黙が覆い始めたと思った時、しいなが言葉を発した。
「難しいことは分かんないよ。でもさ、ゼロスが良い答えを出すことで決着がつくなら、私も協力するよ」
すると蛇が笑う。
「しいな。お前はもう少し“冷たい”人間になれ。その方が、きっといい」
「な……何言うんだよ、突然……」
蛇の低く、穏やかな声と、その言葉は時々、しいなをどきりとさせたものだった。
「言葉通りだ」
蛇は腰を上げる。祝宴とは名ばかりの酒席に酔いも満足ではなかったが、それでも良かった。
「……ありがとう、くちなわ」
二人の間隙を縫って、家成も腰を上げる。
「出直して参りましょう。このままでは、京師に戻ることもままなりません」
すると、しいなは突然、目を瞠り家成を睨視し、声を荒げた。
「場合によっちゃ家成、アンタただじゃすまさないよ。こっちはもう、怖いものはないんだ。分かっているよね」
しいなのすごみに、家成は瞼を閉じて、低頭する。
「ミズホの里は私の生地です。しいな、蛇殿。あなた方は同朋。吝かではありません」
「良い覚悟だ、互いにな」
蛇がにいと笑った。しいなは表裏のない家成の様子に、息を呑んだ。
それから暫くが経ち、木戸のノックと共に、ゼロスの声が響く。しいなは慌てて、彼を迎え入れた。
「悪ぃな。休んでいたか」
疲れた感じの言葉に、しいなは僅かに首を横に振る。
「そんなことはないけど――――あんたこそ、大丈夫なのかい?」
ゼロスの腕にそっと両手を当てながら、しいなは言った。
「どうやら、理性は保たれているみたいだな。もう少し若かったら、反意抑えられなかったぜ」
自嘲するゼロスに、しいなはきゅっと唇を噛み、腕を抓った。
「どこまで嘘か本気か……解らないんだから――――あんたって」
以前はさらと流していたゼロスの言葉ひとつひとつが、今は胸に染み入るようだった。冗談のようで、それが本気。それがゼロスだ。
だからもう、無茶はしないで欲しい。しいなの本心だった。
ゼロスは二、三度しいなの黒く美しい髪を指で梳くと、台所にある甕に溜められた清水を柄杓で掬い、呷った。
「大したもんだぜ、セレスは。さすが、俺の妹だけはある」
「?」
柄杓を戻し、ゼロスはゆっくりとため息をつく。躊躇うように、小刻みに息をつき、唇を振るわせる。自分の心に問答をするように、ゼロスは静かに激しく逡巡し、やがて意を決したように、言った。
「……セレスは判っていた」
「!」
しいなは愕然としてゼロスを見つめる。
「強えぇよ、あいつは――――さすがだ……な」
「ゼロス……まさか――――」
しいなの言葉に、ゼロスは小さく首を横に振る。
「官府の思い通りにさせてなるかよ。セレスが衷心に望まねえ事を、俺はどうしても勧めることは出来ねえ」
静かに、それでもゼロスの言葉は熱がこもっていた。しいなには、彼の想いが痛いほど伝わってくる。
しいなはゆっくりとゼロスに歩み寄ると、その背中に両手を添え、上体を押し当てた。恋人の温もりを感じ、瞼を閉じる。一時凌ぎのような安らぎが、その場所にはある。
「本気……かい?」
背骨の動きが、頷きを示した。
「正々堂々と、アンドリュース卿に対峙しようと思う」
やがて、しいなはすうとため息をついた。
「……セレスは幸福者だね――――」
「……? 何を突然――――」
ゼロスは身を離し、しいなに向き直る。恋人は微笑みを浮かべていたが、その瞳はどことなく哀しい感じの色だった。
「やっぱり、兄妹なんだなあって思ってサ。うん……ゼロス、セレスのことになると違うから」
しかし、ゼロスはいつものように戯けなかった。
無言でしいなを抱き寄せると、愛おしむように背中を撫で、髪に頬を埋めながら、甘酸っぱい香りを吸い込む。。
「あいつには……本当の意味で幸せになって欲しい――――。こんな……俺のような奴でも、慕ってくれている、健気な妹だ。あいつのためなら、鬼にも邪にもなってやるぜ」
ゼロスの背中に回されたしいなの腕に、きゅっと力が入る。
「ゼロス……私と――――……」
思わず言いかけて、しいなは口を噤んだ。それは、言ってはいけない気がした。
「……何でも、ないよ――――」
ゼロスも深く訊かなかった。
「何か……久しぶりだよ――――。しばらく、こうしていて、お願い……」
恋人同士なのに、抱き合うという行為を、二人はあまりすることはない。
昔なじみだからという感覚もあるが、それ以上にふたりを結ぶ“高みの絆”が、二人の信頼関係をより強固なものにしていたのだろうか。心で結ばれた愛。それがあれば、身体を合わせなくても良かった。だから、こうして抱き合えると、より一層、互いの想い、存在、温もりの大切さを解り合える。
わかっているさ――――
セレスはいずれ、俺の許から去り、幸福への高みへと羽ばたくことを……
大きくて、真っ白に輝く翼をセレスは秘めている――――
いつか、その翼を広げて辿りついたエデンの空で――――お前は、俺に向ける笑顔をはるかに超えた、美しい笑顔を向けるのだろう……
俺は……少しでもセレス――――お前の安らぎになれたのか――――
俺は……お前の受けた傷を、少しでも癒せる兄貴でいられるのか……
お前を苦しめない――――。
お前が羽ばたき、眩い輝きを鏤めて昊天を舞うその日が来るまで――――お前は、俺が……
深夜、ゼロスはしいなの家を出た。
「…………」
彼は気づかれないように抜き足を使ったようだったが、無駄だった。しいなもまた、眠れずにいた。ゼロスに気を遣い、眠ったふりをしていたのだ。
ゼロスが出て行ったのを確認し、素肌に木綿のシーツを巻き付けた上体を起こし、木戸を見つめた。
「……ゼロス――――」
“うしみつどき”――――ミズホでは森羅万象が全て幽寂の彼方にあり、熟眠するとされる、夜の中で最も怖ろしい時間。
ゼロスが歩を踏みしめる土の音、石ころを弾く音、衣擦れの音全てが、うるさく静寂に谺する。
一瞬の微睡みが物見の士をも覆う。ゼロスは門を抜け、藤林館の離れに灯の点る部屋へと真っ直ぐに向かった。そこは服部家成の仮宿舎である。
ゼロスは有無も言わずに障子戸を開けた。
「……これはゼロスさん――――」
家成は眠ってはいなかった。まるでゼロスがやってくるかと見越していたかのように落ち着いて言葉を口にする。机に広げた書物。紙と筆が傍らに、さも勉学に勤しんでいる体であった。
「書写ですよ。サイバックでは最近、複写機と呼ばれる便利な機械が導入されましたが、やはり物を憶えるには、自ら握った筆で書き写した方がよいようです。やはり、文明の利器も人智には敵いませんね」
すると、ゼロスが答える。
「権力も同じかよ」
家成は泰然とゼロスに視線を向ける。
「……と、申されますと?」
「どんなに偉くなっても、世界を統べる覇王となっても、人の心は枉げられるものじゃねえ。不変なものだってことよ」
「……なるほど……」
ひとつ間を置き、ゼロスは言った。
「拝覲は出来るか」
「何と……あなた一人で、参朝されるのですか」
「疚しいことはねえだろうが」
静かな声で、ゼロスは圧した。
「…………」
断れば、何をするかわからない。そんな雰囲気が、ひしひしと伝わってきた。家成は真っ直ぐゼロスを見つめ、その意を汲むと瞼を伏せて頷いた。
「ヒルダ様も、アンドリュース閣下も、あなたの参朝を心待ちに致しております。拝覲の準備は常に万全です」
「膳立ては万端という訳かよ」
自嘲するように、ゼロスは笑う。
「カセイ……いや、服部家成。お前もミズホの血を引く漢ならひとつだけ約束しろ」
「はい……」
「てめえの地位や名誉よりも……セレスと、しいなを悲しませることはするな。全てを捨ててでも、守れ」
家成は口許にふっと微笑みを浮かべる。
「それは、ご自分に向けられている言葉とお見受けしてもよろしいですか」
「どっちでもいいぜ。どうせ、ただじゃすまねえだろうからな」
乾いた笑いが妙に響きわたる。それには、家成は無言で、僅かに瞳を逸らした。
「剣は――――佩かれないのですか」
「斬り合いじゃねえ」
余計な言葉を、ゼロスは爽やかに切り返した。
東の空がうっすらと白んできた。日増しに桜の薫りがやや強く漂ってくる。
マナの力が小康状態のために、借りっぱなしのレアバードもそんなに速くは飛べない。ミズホからメルトキオまでは、今から飛んでも春の夕焼けを空から眺望することになりそうだ。
急ぐわけではない。引き延ばそうとすれば、王家はそれを黙認するだろう。しかし、その分、誰よりもセレスが心に痼りを残すことになる。だから、一刻も早く、それを取り除いてやりたかった。
「…………」
レアバードの格納庫に使っている土蔵。ゼロスがそこに来ると、扉の前でしいなが憤然と腕を組み、凭れていた。
「……気づいていたかのかよ。相変わらず、人が悪いぜ」
呆れたように、ゼロスがため息をつく。すでに観念していた。
「その言葉、そっくりアンタに返すよッ」
そう言ってしいなは小さな筒を投げた。反射的にそれをつかみ取るゼロス。
「…………」
蓋を開けると、芳ばしい香りが鼻を擽る。コーヒーだった。
「さんきゅう。悪ぃな」
しいなのコーヒーは旨い。飲まずば一日は始まらないほど、クセになった。
ほろ苦い熱さが、ずきずきするほどの眠気を払拭してゆく。
「私も、連れて行ってくれるんだよね」
「止めても、止めなくても同じだな」
「それでなくても、アンドリュースには、五万と言いたいことがあるんだ。これも、良い機会だと思うし」
「なるほど。そうだったな」
ゼロスが苦笑する。
ふと、しいなが寂しそうな表情を浮かべた。
――――私は……アンタとずっと歩いてゆくよ――――。そう、決めたんだ。
アンタが本気だったから……嬉しいって言うか、上手く言えないんだけどサ……すごくあったかくて――――離れたくないって言うのかな……。
セレスも、アンタと同じくらい私にとっちゃ大事なんだ――――。
だから……アンタ一人に、背負わせないよ。私にも、分けてくれないかい……ゼロス。
ゼロスはにいと白い歯を覗かせて笑い、しいなの頭をごしごしと擦った。
「なあ、しいな……」
「?」
しいなが見上げると、ゼロスは真っ直ぐに、しいなの鳶色の瞳を見つめていた。ゼロスの深く、吸い込まれそうな瞳に、思わずしいなは頬を染める。
「テセアラは……統合世界は、良い国になるか」
「ゼロス……?」
「俺達が取り戻した世界は……これからも、俺達が夢見た世界を保ち続けられるのか」
ゼロスは笑顔だったが、声は隠しきれないほど、震えていた。
ゼロスの身体の芯から、つんとした感覚がこみ上げ、鼻の奥を突いた。思わず、大きな嚔を上げてしまう。
「たはっ……わりぃ、わりぃ。ほんじゃ、まいっちょ、行きますか」
ゼロスは誤魔化すように雰囲気を茶化すと、土蔵の扉を開け放った。
しかし、しいなは彼の胸中に覆う寂しさを知り、見せまいとしながらも、表情を曇らせていた。そして、思った。
どこまで、この兄妹の因果はつづいてゆくのだろうか……と。