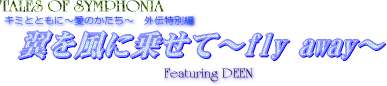
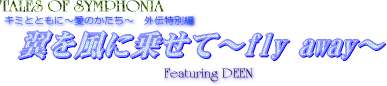
Last Episode.
メルトキオ・東ビーストブルク
ゼロス・ワイルダー邸
ワイルダー家のスチュワード・セヴァスチャンは、公務でメルトキオから離れていた。
ゼロス・セレス兄妹に関連する一連の騒動の余波は、主不在のワイルダー家の公事を、執事を始めとして、下僕にまでしわ寄せが及んでいた。
ゼロスとしいなが久しぶりに自邸の玄関をくぐると、閑散とした空気が冷たく二人を出迎える。多くの家人がセヴァスチャンと同じく出払ってしまっていたからだった。
「おおっ、これはゼロスさま――――!」
ゼロスの姿を見つけ、嬉然として駆けつけてくる、一人の壮年紳士。セレス付きのスチュワード・トクナガであった。
南洋修道院から出奔した時、ゼロスの計らいでワイルダー邸に匿われ、そのままセヴァスチャンの片腕としてワイルダー家の庶務に当たっていた。
「トクナガ、随分と留守を預かってもらって悪いな」
「何を申されます。ご兄妹の御為ならばこのトクナガ、犬馬の労も厭いませぬ。……ところで、セレス様は――――」
トクナガが視線を移す。どうやら、彼は事情に通じていない様子であった。
ゼロスは不安げに視線を揺らしているしいなと瞳を合わせると、ゆっくりと頷き、トクナガを見た。
「トクナガ――――」
「は、ははっ」
淡々とした口調を装うゼロスに対し、妙に畏まるトクナガ。
「セレスは……煩わしくはなかったか」
「――――は?」
突然、そんなことを言うゼロスに、トクナガは戸惑った。
「これからも、お前の事が必要だと思っても、迷惑にはならないか」
その真剣に満ちた表情と言葉を、トクナガは推量した。
「……身命を賭して――――」
「ありがとう」
ゼロスがしっかりとトクナガの手を握りしめる。
「ゼロス様――――何を」
懸念するトクナガに、ゼロスは微笑みを向ける。
「案ずるな。ただ……それを訊きたかっただけだ」
「セレス様は……」
「…………」
「セレス様は……、心から御兄上様をお慕い致しております――――。どうか、その御心、安んじられますよう――――このトクナガ、伏してお願い申し上げます……」
ゼロスはひとつ、大きく頷いた。
メルトキオの夜は相も変わらず華やかさに満ちていた。
ワイルダー邸がある東ビーストブルクは、貴族街の中でも郊外の方にあるため緩やかな坂道が続く。爛々としたイリュージョンに擬した貴族街の灯り、城下を彩る生活の灯り。
思えば、ゼロスが着飾った殿上人の生活に呑み込まれることなく、気さくで俗っぽい性格を培ったのは、幼い頃からこうした街の灯りを見つめつづけ、庶民の生活の匂いに触れてきたからなのかも知れない。
「少しは、寝た方が良いんじゃないのかい?」
不意にしいなが言葉をかけてきた。
「心配すんな。少しばかり夜型のリズムが直らねえだけだからな」
戯けるゼロス。「バカ…」と、呆れるしいな。いつものようなやり取りを交わすだけの、穏やかな夜なのに、何かが違っている。
「なあに、湿気た面してやがる」
突然、ゼロスがしいなの額を小突いた。あっと驚くしいな。
「湿気た面――――じゃないよ。ずっと、あんたのこと心配してるんじゃないか」
そう言えば、しいなはこのところずっと、ゼロスを見つめつづけているような気がした。
今の彼を見れば、意気消沈もするだろう。
「安心しろって。何度も言うが、これは俺と、セレスの問題だ。他愛もねえ……問題なんだからな」
「…………あんたらしいねえ――――そう言うところ」
ため息をつくしいな。
「一応、誉め言葉として受けとっておくぜ」
「胸の裡は、決まったのかい? それだけでも、聞かせてくれないか」
「…………決まった。全ては、俺なりにあいつのためになる道を選んだつもりだ。後悔はしねえさ」
「そう――――そっか」
わずかに寂しそうなしいなの横顔。
するとゼロスは徐に恋人の肩を抱き寄せると、揺れる鳶色の瞳をのぞき込むようにして、にいと笑った。
「な、なによゼロス」
雰囲気もなく抱き寄せられ、しいなは動揺する。そして、決まってこういう時に限って、彼は間の悪い事を言うのだ。
一緒に――――ならねえか――――
……………………え……………………?
一瞬、しいなの意識が遠く白んだ。くらくらと、輝いた光の粒が、光芒となって瞳を掠める。
それは、しいなの言葉を封じるかのような時宜。不意打ちとはまさにこのこと。
「そんな…………いきなり…………」
次第に鼓動が強く、速くなって行くのを感じるしいな。恥ずかしさから身を離そうとするが、ゼロスの逞しい腕に抱かれた身体は離れなかった。しいなもすぐに諦めた。顔が真っ赤に染まり、俯く。言葉を失い、唇を噛む。
不意打ちの求婚。気の利いた言葉すら思い浮かばない。大事な時にいつもこうだ。ゼロスといると、いつもそれがもどかしい。
心に残る、恋人との光景。それがゼロスとしいなにとっては、全てがどこかしか滑稽なもの。凸凹カップルと誰かが言う。
きっと、ゼロスとしいなは、他の幸福に満ちた恋人達のように、甘く楽しい笑顔に満ち溢れたアルバムを、半世紀の後に懐古するようなものではないのだろう。
だが、しいなはそれでも良いと思った。
ゼロスがそこにいてくれる。何かにつけ戯け、茶化しても、彼の存在を感じ、その肌の温もりを受けられる喜びは、誰にも負けず、何にも代え難い幸福に他ならなかった。
しかし、人生のひとつの節目。その言葉くらいは、それなりの雰囲気を作った中で、或いはそんな雰囲気の中で欲しかったと、しいなは柄にもない乙女心を思った。
ゼロスは小さく苦笑いを浮かべると、そっと恋人の額に唇を寄せ、優しげに囁いた。
「全てに、ケリがついてからでいいさ……」
「ゼロス……私は……」
嬉しい。嬉しいけど、思うように言葉がまとまらない。胸の高鳴りが、ますます混乱させる。
「ああ、わかってる。しいな……お前はマジ、俺には過ぎた女だぜ」
「…………」
しいながそっと、ゼロスの胸にしがみつく。
「今は……こうしていてもいいだろ」
忘れたかった。無性に、何もかも忘れたかった。
「今だけじゃなくても……いい…………」
しいなはやっとそう言葉を発し、上体を動かしてゼロスを胸に抱いた。柔らかな恋人の胸に貌を埋めてゆくうちに、ひとときでも安らかな心地に導かれてゆく。それが何よりも嬉しく思えた。
朝靄が未だ晴れぬ早暁。その清晨に包まれたワイルダー邸の門前に、馬の嘶きが響きわたる。
庭園を掃き清めていた女中(メイド)が、訝しげに箒を置き、小走りに馭者へ駆け寄る。
少しの間馭者と話をしていた女中は愕然としたように身を竦め、慌てて邸内へと向かって駆けた。髪を束ねるヘアバンドが振り落ちそうになるのも構わない。
「ゼロスさま、ゼロスさまっ!」
どんどんと寝所の扉を叩きつける女中。ゼロスの返答も待たずに、扉を開ける。
「王室の御使者が――――」
しかし、返ってくるのは激怒の声。許しもなく扉を開くのはあるまじき非礼。
しかし……
「慌てなくても良いぜ。戦闘準備は、万端だ」
優しく、戯けたようないつものゼロスの声だった。女中は慌てて非礼を恥じたが、ゼロスは手のひらを翳して不問に付した。
「今朝のビスケットは特段上手く焼いてくれたかい」
「は、はい……間もなく、焼き上がるかと」
「重畳。君は良くできた女性だ、キャロル」
普段とは違い、首・手以外の露出を控えた、煩い刺繍や飾りのない、シックな白銀の朝衣を纏ったゼロス。しいなはかつて晩餐会に前国王マリウスから贈られたドレスを身に纏い、宝剣をゼロスの腰に差した。
「すぐに発つんだよね。……うん、いつでも良いよ」
ゼロスの襟元のスカーフのずれを直すしいなの様子は、すでに賢妻の様相を湛えている。
「キャロルのクッキーと、しいなのコーヒーがあれば、それでいいぜ」
しいなの手をそっと握り、立ち上がる。
「ばか言ってんじゃないよ」
軽くあしらうとゼロスの背中をとんと叩き、寝室を出た。
国主・法王が在する太聖殿、マーテル教会の聖堂がある西殿、王族のプライベートな住居となる東殿。メルトキオの宮城はひとえにかなり広い。
漸く真っ白な陽光がグラン・テセアラブリッジの橋梁を照らす頃、中央政庁兼衛門とも言うべき南殿へと、二人を乗せた馬車が辿りついた。
徹夜明けの衛士の眠そうな表情、省庁勤めの官吏たちの出勤風景が垣間見える。
窮地から脱し、統合世界への道筋が明らかになったこの時こそ、彼らは休む間もない。
脅威を祓い、世界を統合する大役はゼロスたちが果たした。しかし、その脅威の最中で攪乱した人心の安定、治安、物価、外交……庶民の日常生活に欠かすことの出来ない細事をこなしてゆくのが、テセアラ王家を元首とする政府である。その政府が今、前国王マリウスの退位後、ヒルダ女王・アンドリュース国務大臣の下で、テセアラは立憲君主制の共和国家へ生まれ変わろうとしている。庶民は平和が戻ったとしても、『お上』、『お役人』には休む間もなく、ともすれば恐怖に満ちていた時代よりも激務になったかも知れない。
南殿の廊下。王立研究院で軟禁・酷使されていたハーフエルフの学士たちの姿も見える。
案内を受けて、ゼロスとしいなは貴賓室に控えた。
「アンドリュース卿は、ハーフエルフ法を事実上廃案へと持ち込む布石として、科学教育省の創設を提示したと。ヒルダ様もそれを推奨し、折り紙付きで認めたらしいぜ」
宮城を歩く科学教育省の『官僚』ハーフエルフ。以前では考えられなかった光景。
しかも、科学教育省の初代大臣にはケイトの名も挙がっていた。しかし、これはさすがのアンドリュース卿も、諸侯の猛反発にあって断念したという。
「少し……強引だねえ」
しいながふとそう呟く。
「だてに、急進派の旗頭だったわけじゃねえ……ってことだな」
ゼロスが半ば失笑する。
「下手をすりゃ――――」
しいなが言いかけた時だった。ただならぬ気配を感じたゼロスが貴賓室の扉に視線を向ける。
「覚悟は出来ているさ。互いにな」
その言葉と同時に、扉が開いた。
長身痩躯の、文字通り美丈夫が姿を見せた。前政権の失脚後、権力の頂点にある国務大臣にしては、意外にも簡潔な朝衣を纏っていて、決して高圧的な雰囲気を漂わせていない。
清廉潔白という言葉が合うかどうかは別としても、ゼロス、しいなと、目を合わせ、ゆっくりと拝礼する姿には、権力者特有の驕慢さは微塵も感じられなかった。
「ゼロス殿、藤林の姫御前。ご無沙汰致しておりました」
低音で良く透る声。恭謙で、耳当たりがよい。
二人はソファから立ち上がり、この廉士に対し拝礼する。
「ご挨拶が遅れた非礼、御容赦を。アンドリュース閣下」
形式張った挨拶はすぐに済ませた。
「貴族の礼は不要だ、ゼロス殿。女王陛下も、ご配慮下される」
「御言葉に従いましょうか――――」
アーネスト・アンドリュース。元フラノール辺境公。国務大臣・経財相を経て、今はヒルダ女王が任命した、暫定首相職にある、事実上のテセアラ政府の最高指導者だ。
「フラノールバーボンをこよなく愛するおっさんには積もる話もあるが、アンドリュース宰相閣下には、ちょっくら辛みしかないなあ」
「手厳しいな……まあ、それも致し方ないだろうか」
アンドリュースは二人を先にソファを勧めると、女官に目配せをする。
「回りくどいことは言わないよ。結局、あんたもカーネルと同じ事をしようとしているだけじゃないか」
しいながすごんだ。その言葉を予見していたのか、アンドリュースはおうむ返しに言った。
「姫御前、それは大きな間違いです。国を想い、人心を束ねうる身、ただ栄達を図り亡国の片棒を担ごうとした者ではありません。このアンドリュース、ただテセアラの士師でありたいと願うだけです」
「難しい御託はいいよ。私が言いたいのは――――!」
すっ――――と、ゼロスの掌が伸び、しいなの口を覆う。愕然とするしいな、眉を寄せてゼロスを睨みつける。
ゼロスはしいなを一瞥し軽く宥めると、アンドリュースに言った。
「主上の御前で、俺の気持ちは伝える。それが、人臣としての礼だろう、宰相閣下」
「構わない。それよりも今は、フラノールバーボンを酌み交わした、朋友として話をしようじゃないか」
「ああ……しかしこう煌びやかな空間じゃ、言葉が途切れてしまうけどね」
程なくして女官が淹れたての香茶を蓄えた魔法瓶をのせたトレイを運んでくる。
ゼロスとしいな、アンドリュースは短い時間だけ、わずかに旧交を温めた。立場が変わると、人の絆の形も変わってゆく。人と、人とのつながりというものは、そういうものなのだ。
魔法瓶に程良く沸かされた香茶を飲み干した頃、アンドリュースは言った。
「そろそろ、拝謁の頃合です」
「……なかなか美味かったぜ、閣下」
「ちょっと、苦みが強いけどね」
ゼロスとしいながそう言って苦笑する。
「更に精進しましょう。次はゼロス殿の舌を鳴らす程に――――」
含みを込めるアンドリュース。そして、ふっと口の端に微笑みを浮かべてから、朋友より、政治家の顔に戻った。
繁栄世界・テセアラの天上界を思わせた王城・玉座の間。テセアラ王室歴代の君主が世界を遍く統べていた瓊玉の空間も、時代と共に変化を感じさせていると思わせるほど、そこはかとなく寂寞として広い。
前国王マリウスが退位され、王女のヒルダが踐祚・登極し、それを宣布されてから、ますますそれが顕著になってきた。
ヒルダ女王陛下も、即位されてから二年に満たないはずなのに、いささか容姿に疲労の色が滲み、湛える笑顔も心なしか覚束無い。
かつては親ゼロスを公言して憚らず、父王や侍臣から窘められた事もあった。
王女としての品格を失うことなく、かつゼロスを気遣う優しき美姫。ヒルダ姫にとって、父の突然の退位は当に青天の霹靂。そして何よりもヒルダ姫自身の人生を一八〇度転換させるに等しい出来事であっただろう。
女王陛下、暫定首相、そして無役の英雄二人だけの空間は妙な緊張感の中にあった。女王陛下の宸襟を察し、廷臣の参内をアンドリュースが手控えさせたという。
「ゼロス=ワイルダー、御前に。陛下にあらせられましてはご機嫌麗しく――――」
ゼロスに続いて、しいなも形式張った挨拶をする。姫はにこりと微笑む。
「二人とも、元気そうで何よりです」
久しぶりに耳にした姫の言葉。記憶よりも少し違和感がある、楚々とした口調だった。
「首相も大儀です」
「ははっ」
それは毎日のように口勅と奏上を交わす君臣のやり取り。アンドリュースが言うように、諸事万端は完璧に調われていた。ヒルダ女王も、かつて特別の想いを寄せていた、ゼロス=ワイルダーを一人の人民として接し、本題を呈す。
「宣旨はそなたに伝えられているはずです。そなたの胸の裡、聞かせてもらえますか」
女王陛下はそう曰いながら、徐に玉座から腰を上げる。驚くアンドリュース。ゼロスとしいなは恭々と拝礼をする。
コッ……コッ……
沓の音がゆっくりとゼロス達に近づき、遠く谺する。
「その前に……」
女王陛下の声に、反射的に顔を上げたゼロスとしいな。次の瞬間、二人は愕然となった。
陛下は何を思ったのか、ゆっくりと片膝を折り、竜扇を組み合わせた両手に挟めると、ゼロスに対し、頭を傾けたのである。
「へ、陛下ッ!」
「!」
「ヒ、ヒルダ姫さまっ!」
それは属国の王侯が入朝した際に、宗主に対し忠誠を誓う意の拝礼。一国の王が人臣に対して向ける事など、あり得ないものなのだ。
ゼロスは慌てるように身を乗り出し、ヒルダ姫の御手を取る。
「おやめ下さいヒルダ陛下。畏くも聖テセアラの君主たる御方が、人臣に跪くなどあってはなりません」
アンドリュースの諫言よりも先に、ゼロスはその美しき紅の髪を絨緞に撒き散らし、額を擦りつける程に低頭し、諫めていた。
「ゼロス……私は――――」
そっと、囁くようにヒルダ姫は唇を動かす。
しかし、ゼロスは毅然とした意志を示すように言った。
「ご宸意、このゼロス・ワイルダー、深く身に染みてございます――――。今、ようやく一縷の迷い、祓われた心地です」
「…………」
しいなが真っ直ぐゼロスを見つめ、わずかに息を凝らした。
ヒルダ姫を玉座に導き、君臣の秩序を辛うじて守ったゼロスは、女王陛下とアンドリュースを、同じ視界に入れるまで後退し、息を整えた。
「憚りながら、妹セレスのこと――――」
その時だった。
――――――――お兄さま――――――――!
磨かれたばかりの鈴のように玲瓏とした声が、太聖殿の間に反響する。
「!?」
愕然となり振り返るゼロス。
「な――――何やってんだいアンタッ」
しいなも思わず場を忘れて素っ頓狂な声を張り上げる。
衛士の制止もお構いなしに、セレスはオリーブの大きな帽子を揺らしながら、つかつかと毛氈に小さな足跡を刻んでゆく。
唖然とするゼロス。呆然とするアンドリュース。思わぬ人物に目を瞠る女王陛下。混乱するしいな。
それぞれのらしき反応を一通り確かめると、セレスは臆面もなく、女王陛下を凝視した。
――――私、公室に身を置くことを決めましたわ――――
その言葉が、特別な音色となって、延々と谺する。
「セレスッ」
ゼロスは大きな声を上げた。しかし、今までに見ぬ妹の凛とした表情と厳しい声色に、ゼロスは圧倒され、二の句を継げなかった。
「テセアラのために……そして何よりもお兄さまのためになるのでしたら、私……喜んで、女主となり、民と平和にこの身捧げますわ――――」
「まあ、セレス……それは、まことですか」
女王陛下が再び立ち上がり、セレスに歩み寄る。ようやく、セレスは跪き、ほんの少しだけぎこちなく、帽子を外し、傍らに置いた。
ゼロスと同じ、美事なほどの紅のショートヘア。その毛先がテセアラの風を受け、わずかに乱れていた。
「女王陛下の御前で偽りなど申しましょうか」
凛とした声で、セレスは微笑んでいた。
「蛇、ありがとう」
夜半も過ぎても、玄関扉の脇に凝立していた蛇に、ゼロスは礼を言った。
「姫神子の意志だ。神子が如何様な答えを出そうが、俺は姫神子の意志を重んじるまで」
「……君には、言っておこうか」
そう言うゼロスに、蛇は掌を翳し、強く拒絶した。
「惑うな神子。俺はただ、凶刃から命を守り、障りを除くのみ。それが俺なりの贖罪だからな」
蛇の配慮に、ゼロスは無言でその手を握り、肩を叩いて労った。
セレスとしいなはあれから間もなく退朝していた。
ゼロスは随分と久しぶりの登城に顔なじみの群臣諸侯から足止めをさせられ、またセレスに対する尚早たる祝賀を受けていた。しかし、勧められ、酌み交わす酒も一向に酔えないまま、満天の星明かりが照らす坂を伝った。
「お帰り、午前様」
リビングの広間で、しいなが呆れたようにゼロスを迎えた。
「酔えねえ酒ほど、不味いものはねえな」
そう言って苦笑するゼロス。
「セレスは、もう寝たか」
「…………来なよ――――」
しいなはそう言って、ゼロスをゼロスの寝室に導く。
そっと扉を開け、中に入ると、セレスはゼロスの寝台で眠っていた。
しかし、その寝顔を確かめようと身を乗り出したゼロスは愕然となり、思わず両手を口に押し当てた。
「無理してたんだよね――――きっと」
どうせ眠れないだろう。しいなはコーヒーを淹れてくれた。しいなのコーヒー。くせになっていた美味の嗜好も、喉を通らない。
「それでも俺は――――セレスを手放さなければならねえ」
その言葉に、しいなは思わず声を張り上げた。
「見損なったよ。あんたらしくないねえ!」
だが、ゼロスは力なさげにぽつりぽつりと話し始める。
「聞けよ、しいな――――俺達ワイルダー家は、代々マナの神子としての宿命を背負っていた」
「そんなことはわかっているサ」
……全てはテセアラのため、民のためという名分のもとで、俺達はこの血を呪われたものだと思いながら生き続けてきた。
俺とセレスも、そんな輪廻に翻弄されながら、互いを愛し、憎しみつづけてきた。
世界が一つになって、俺たちを雁字搦めにしてきた鉄の鎖は切り落とされた。
お陰で、俺とセレスはやっと、『兄妹』になれた……。
でも――――でもなしいな。
本当の意味で、輪廻を断ち切れたことを感じることは出来ないままだった。
またいつか、俺たちを引き裂く運命に遭遇するのか――――。統合世界を掻き乱す火種とならないか…………。
セレスが至上を継ぐことで、ワイルダー家……いや、テセアラの悲劇の輪廻に、本当の意味で終止符を打てるのなら、俺はそれを受け入れよう。
……これが最後の苦しみ――――
……これが……最後の涙だ――――
「オカシイ……おかしいよゼロス。そんなの、セレスの本心なんかじゃないよ」
しいなの声は震えていた。ゼロスもまた、懸命に動揺を抑え込み、平静を保とうとしている。
「鵬(おおとり)は内に秘めてちゃ意味がねえ。高天を舞い、テセアラにその美徳を遍く示すことが大事なんだ」
「鵬……? セレスが鵬だって言うのかい?」
瞳を赤くしたしいなが問うと、ゼロスはゆっくりと頷いた。
「あいつは……きっと、多くの人に愛される――――。あいつは……抑圧され、虐げられ……孤独に悲しむ者たちの心を、誰よりも解ることの出来る優しい人間だ。……荒み、傷つき――――そしてこれから始まる新しい世界を導く君主として、これ以上にない立派な人間だと思う」
それが贔屓目でないことを、しいなは痛いほどよく解っている。
「あいつの背中にある輝く翼を、俺たちの過去に縋って独り占めなんて出来ねえよ。二人……十人……百人……千人……もっと、もっと多くの連中がその翼に包まれる方が良い」
「ゼロス…………」
しいなは笑顔を浮かべるゼロスを見て、急激に熱いものがこみ上げてきた。顔が熱くなり、目頭が沸騰する。
「セレスはきっと、そこに生き甲斐を見つけてくれるはずだ……。――――うひゃひゃ、伊達に兄妹じゃねえっつうの? 何となく解るんだよなー」
久しぶりのゼロスの笑い。それはそこはかとなく乾いていて、砕けてしまいそうな感じだった。
「…………」
しいなは眦から頬に伝った透明な線を消すこともなく、腕をゼロスの頸に絡め、徐に唇を重ねた。
「し、しいな?」
突然、積極的な恋人の様子に戸惑うゼロス。
「いいのかい……? 本当に、あんた――――それでいいのかい?」
ゼロスは言った。
「断ち切った鎖の――――填めた手枷・足枷は、後世には遺さねえ」
しいなはそれ以上何も言わなかった。
ゼロスとセレス。この兄妹が歩んできた道。苛酷な因果が培った固い絆。そんな二人が導いた答え。たとえそれがどの様な答えだったとしても、間違いじゃないのだから……。
東ビーストブルク坂を下り、爛々と灯りが連なる城下に向けて歩く二つの影。
「そうか……辞めていたのか」
王立研究院参事を辞職していたことを、笑いながら告白した服部家成に、蛇は飄然とした表情を向ける。
「あのお二方の出す答えは……何となく解っていましたから――――。結局、何の抵抗にもなれませんでしたけれどね……」
自嘲するように笑う家成。
「お前らしいな」
「自分でも時々ウンザリしますよ」
「それで――――お前はこれからどうするのだ?」
「私も英雄に倣い、諸国巡礼にでも出ようかと」
「そうか」
引き留めない蛇。家成は穏やかに笑っている。
「もう、遇うことはないな――――」
「皆さんに、お伝えを。『報国尽忠の士、ここにあり』と」
戯ける家成に蛇は失笑した。
「最後くらい、何も忘れて飲もうか、家成」
「同感です」
肩を組み合いながら、ミズホのカゲたちは城下に繰り出していった。
セレス・ワイルダーが東殿に入ってから一年。テセアラはヒルダ女王、アンドリュース暫定首相を主軸に、新憲法制定の気運が一段と高くなってきていた。
今やハーフエルフを虐げてきた事に代表する旧体制の崩壊は、世情を見るにも顕著で、統合世界の民主化は長期的な展望に漸く安心感を見出せるまでになった。
そんな静かな激動の世情の中にあっても、ミズホの里は相も変わらず、穏やかな時にある。
桜花が舞う蓬莱の山脈。シルヴァラント、そして里を照らす篝火に、薄紅の雨が津々と降り続く。
華燭の典――――。それはいつになく盛大に、執り行われようとしていた。
毬栗老・藤林保豊が隠棲。保興が総領となり、藤林家の後嗣・しいなが事実上の次期総領となった。これを契機に、やっと、しいなとゼロスの長年の夢が叶おうとしていたのだ。
ゼロスから、馬子にも衣装などと良く揶揄された、しいなの白無垢。かく言う新郎も、羽織袴なぞ実に不釣り合い。
金屏風に飾られた上段に、ミズホ伝来のいわゆる雛人形の如く鎮座する二人。
「…………」
「…………」
柄でもない。妙な緊張と気恥ずかしさで、コチコチに凝り固まる。
(セレスに報せとけば良かったか?)
(今更なに言ってんだい)
すまし笑顔で罵り合える、素敵な関係。
粛々と、結婚の儀式が進んでゆく。
神官が、契りの杯を掲げ、二人の前に進み出た。
その時、暖かな風がふわりと、そこに桜花を運んできた。杯の御酒に、一枚花弁が落ちる。
「おお、なんて風流な」
雰囲気の美しさに、思わず神官が言葉を発した直後だった。
風が一瞬だけ強く吹き込み、新郎新婦を包んだ。
「ぎゃ!」
風流などとは程遠い、杯にはてんこ盛りにでもなりそうなほどに花弁が積もっていた。間抜けな叫び声を上げてしまうゼロス。
「ちょ、ちょっと!」
すましていたしいな、たがが外れたかのように身を乗り出す。そして……。
お待ちになって――――下さいませ――――ですわ――――!
それはきっと、どんなに離れていようとも、どんなに時が経っていようとも、一度耳にすればすぐ間近な、聞きなれた愛おしい声音なのだろう。
「――――――――!」
「え――――――――!」
唖然となる二人、驚愕し、騒ぎ出す出席者たち。
だ――――め――――で――――すぅ――――わぁ――――!!
穏やかで、心休まる蓬莱の麓の神秘の里。忘れかけた、良き時代の何かがある場所。
それでもひとつくらい、こんな賑やかなものがあっても良いじゃないか。
幸福の意味……世界の平和……安らぎ――――。
求める真実の答えはひとつじゃない。そして、これからも、それはきっと、解らないのかも知れない。
それでも、ここにいる人たちの喜びに満ちた表情が、ひとつの示唆になっているような気がした。
翼を風に乗せて~fly away~