![]()
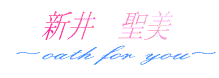
そこに立つのはそう、もう6年にもなるのだろうか。
私の中で、懐かしさと共に、まわりの時間がゆっくりと止まり、そして遡って行くような気がした。変わらぬ風景、変わらぬ校舎、そして、あの生徒たちと卒業記念にと植えた翌檜がいつしか見上げるばかりにそびえ、うっすらと雪化粧をしている。
31年生き、今日まで6年の教師生活を過ごしてきた。数多くの人々や生徒たちと触れて来たが、新米としてこの学校で教鞭を奮った一年間ほど、印象強い思い出はなかったような気がする。
『有馬先生へ
同窓会を兼ねて、クリスマスパーティをします。先生もぜひぜひ来てね!』
突然その手紙を受け取ったとき、私は無性に身体の中が熱くなるのを感じた。見覚えのある、雑だがそれでもしっかりとした文字。最後に『加藤美夏より』とあった。
私は導かれるように新幹線に駆け込み、二時間をかけ再びこの懐かしい地へと足を踏んだ。スピードが落ちてゆくと同時に、胸の高鳴りが増す。そしてドアが開き暖かな車内から粉雪ちらつくプラットフォームに降りたとき、肌に感じる寒さよりも心の中に暖かなそよ風が吹き付ける感覚にとらわれた。
腕時計は午後5時。周囲はすでに夜。パーティの予定は7時。早くたどり着いた私は、パーティが開かれる加藤の家『長寿庵』には向かわず、無意識にこの校舎の前に立っていたのだ。
今日はクリスマス・イブ。人々が愛を語る日とされる、一年最後のイベント。だが、私には今は恋人がいない。31にもなって独り身などと親や友人たちから馬鹿にされることもあるが、私は気にしていなかった。仕事が忙しいからそんな暇がないと言い訳しているが、本当に、不思議と誰とも結婚したいという気持ちにはならなかった。
何度目になるだろう、ひとりのクリスマス・イブ。だが、今年はそうならなかったようだ。1900年代最後のこのイベントを、教師という道のスタートの年に受け持った愛する生徒たちと過ごせる。これ以上の幸せがあるだろうか。
私はその人生のスタートラインに立ちながら、真っ白な真綿に水がしみこむように広がってゆく感動に目頭が熱くなっていた。
「帰って、きたんだ……」 無意識のうちに、私はそう、呟いていた。そして、誰もいなくなった校庭へと、歩を進める。止まない粉雪がゆらりゆらりと舞う。夜更けにはきっと景色を彩るだろう、ホワイトクリスマス。
(あの頃も、同じだった気がするな…) 校庭の真ん中に佇みながら、外灯の淡い光に照らされた校舎を見回してみる。脳裏によみがえる光景が重なる。何も変わっていなかった。
しばらく物思いに耽っていた私だったが、やがて誰かが近づいてくる気配にはっとなり、振り返る。
校門の方に向けられた視線の先から、ひとつのシルエットがゆっくりと私の方に近づいてくる。私はじっと見つめた。見覚えのある影。徐々に目が慣れてゆく。そして、その姿を認識出来たとき、相手が言葉を発した。
「センセ」 懐かしげに、そして愛おしさと哀しさ、喜び、ありとあらゆる感情がこもった声で、その女性は私の名を呼んだ。
「ん?……もしかして――――新井……聖美か?」 私の問いかけを肯定するように、彼女の口許から、はあと白い息が漏れ、外灯の淡い光がそれを照らす。
「遅かったね……」 彼女は優しく微笑んだ。
「え……?」
きょとんとなった私の顔を見つめて、彼女はまた、ため息をつく。
「あの時の約束、憶えてる?」
「…………」 私は彼女をじっと見つめたまま、何も答えられない。彼女はひとつ哀しげにため息をつくと、しおらしい声で言った。
「6年間、ずっと待ってた……」 何かをこらえるように、彼女は長い睫をそっと伏せる。
学生だった時、彼女はすこぶる素行が悪くて、不良という名に相応しい問題児だった。私が清華に着任し、3年B組を受け持ったとき、彼女や加藤を含めて5人の生徒に寝る島も与えられなかった。
特に彼女――――新井聖美は私に猛反発し、学校を休み、喫煙、飲酒、バイク通学などことごとく校則に違反しつづけた。私が彼女を気にかけると、それが却ってひどくなってゆく。
私にはわからなかった。なぜ彼女がそこまで私に反抗するのか。罵声を飛ばし、逃げ出そうとする彼女の腕をつかんだときに振り返りざまに私に向ける視線が、怒りと憎しみに震えていた。
「私は憎まれている」そう、思っていた。
12月24日。
私は前に買っていた、クラス全員へのクリスマスプレゼントであるオルゴールを、終業のHRでひとりひとりに手渡した。歓喜の声渦巻く教室。だが、その日、彼女は学校を休んでいだ。毎度のことだったが、私はその時に限って妙にいやな予感がしていた。
そして、予感は的中した。職員室に戻った私が見たのは、教頭を囲みながらいきり立つ教師たち。私はその理由を聞いたとき、愕然となり、声を失ったのだ。
――――新井聖美、退学処分――――
前日、彼女はいつものように街を徘徊していたが、他の不良といさかいを起こし、相手のひとりを入院させるまで怪我を負わせ、警察に補導されたのだという。彼女の父親が身柄を引き取ったが、ついさっき警察の方から学校に連絡が来てこの騒ぎになった。彼女の家に電話したが、彼女は不在だった。
今まではどんなに素行が悪くても、そのようなことはなかった。私にはわかっていた。彼女の優しさを、心の純粋さを。
私はいきり立つ教師たちの間に割り込み、必死で処分保留を嘆願した。何度頭を下げ、何度土下座したか憶えていない。だが、教頭は私の熱意をわかってくれたのか、もうしばらく様子を見ると言ってくれた。彼女のことは私に一任すると。
私は思わず大声で礼を言うと、取るものもとらずに校舎を飛び出した。
街を飾るイルミネーション、街角に流れてゆくクリスマスソング、静に舞う粉雪。沿道を寄り添いながら歩いてゆく恋人たち。私はひとり、息を切らしながら聖夜の街を駆け回る。
そんなことはいつものことだった。人から言わせればもしかすると、自分の受け持った生徒が卒業寸前で退学ともなると、それこそ面子に関わるという、それだけの理由だったのかも知れない。だが、私はそうではなかった。不思議なほど彼女のことを気にかけていた。そして、ようやく私は自分の気持ちに気がついたのだ。
彼女が立ち寄りそうな場所を駆け巡る。彼女は仲間と連むようなタイプじゃない。繁華街を見回しても、人波の中に彼女の姿はないと私は確信していた。
イブの夜も更けてゆく。午後11時。普段、喧噪鳴り止まないこの街も、不思議なほど静かになってゆく。うっすらと道を覆う雪に刻む足跡の音がはっきりと聞こえる。
その時、私の脳裏に突然、ある場面が過ぎった。
それは私が清華に着任した初日。教師のくせにいきなり遅刻しそうになり、大慌てで出勤。校門ではち合わせしてしまい、結局予鈴に間に合わなかったこと。それが、彼女であった。
着任早々遅刻した『教師』と知って、彼女は一瞬だったが笑った。その微笑みが今まで私に見せた、本当の笑顔だった。
舞い下りる雪に彩られた街が、淡い光に照らされ銀色映える。美しい聖夜の銀世界を、私は自然と彼女と最初に出会った校舎へと向かっていた。
やがて角を曲がり、校舎へと目を向けたとき、私の足はぴたりと止まった。
誰もいない道。校門に凭れながら、しゃがみ込むひとりの少女の姿を見たとき、私は心の底から安堵した。勢いよく駆け寄り、怒鳴るという気持ちは更々感じなかった。
私はゆっくりと彼女の元へと歩を進める。足音に気がついたのか、俯いていた彼女の顔が上がり、私の方に向く。別段、驚いたような表情はしなかった。むしろ、私が来ることを知っていたかのように、わずかに微笑んでいるように見えた。
(新井……)私は彼女の前に立ちすくみ、息をつく。彼女は私の顔を見上げると、寂しそうに笑った。
(あんたなら……きっと来てくれるだろうと思っていたよ……) いつものような口調で、彼女は言った。
私は何も問い質さなかった。ただ、小さく頷くと、ゆっくりと彼女の傍らにしゃがみ込む。こんな事になった経緯を聞こうともしない私を、彼女はどう思っていたのだろう。時折、私の方を見る視線を感じながら、私はただ安堵の微笑みを浮かべていた。
(間に合って、良かったよ……) そう言って、私はコートのポケットから彼女に贈る、オルゴールの包みを取り出し、差し出す。
一瞬、戸惑った彼女だったが、ゆっくりと手をさしのべ、それを手に取った。気づかないように顔を伏せてはいたが、その頬がうっすらと赤く染まったのを、私は忘れない。
それからしばらくの間、私たちは一言も言葉を交わさなかった。無言が心を伝えるという格好つけた事だったのかはわからない。だが、少なくても何かが互いに伝わった事だけは確信できた。そして、沈黙を破ったのは、彼女の方だった。
(アリマセンセ……あたし……ずっと……) それは紛れもない、私に対する愛の告白であった。出逢ったときから、彼女は私に惹かれていた。どんな問題を起こしても、必死で庇う私の姿を見ているうちに、その気持ちは強くなっていたのだという。だが、心のどこかで拒絶するものが、彼女の反抗心を呷っていった。時が経つにつれ、私や周囲に反発していったのは、自分の気持ちをむりやり封じ込めようとするための、心ない行動であったのだと。
結果的に、クリスマス・イブ前夜の補導事件は、彼女の心を素直にさせるきっかけになったと言える。彼女は信じていた。私が必ず自分を捜してくれるものだと。それは毎度のことだったが、今日は決してうざったいという感情は微塵も抱かなかった。かえって私を待っていてくれた。私と、彼女が最初に出会った、この場所で。
私はそっと彼女の肩を引き寄せた。うっすらと積もった雪がサラサラと滑り落ちる。冷え切った彼女の身体は震えていた。抵抗することもなく、コートに包まれる彼女の頬が、そっと私の胸に預けられる。それが、私の答えであった。教師と生徒という関係が今まで二人の間に壁を作っていた。惹かれ合うもどかしさに、彼女だけではなく、私自身もどこかで苛立っていたのかも知れない。それが、奇しくも補導事件をきっかけに、イブという特別な日に崩れ去ったことは、何にも増して大きい。
(センセ……あたし……) 感情のこもった声で、彼女は口を開いた。言いたいことは判っていた。私も同じ気持ちだった。
(来年――――今日この日に、君を迎えたい――――) 彼女の言いかけた言葉を、私が先に口にする。彼女は驚いたように私を見つめる。
卒業したら一緒になろうと言いたかった。だが、私はただ感情に流されるまま彼女と一緒になることを憚った。12月24日、ようやくお互いが素直になれたこの記念日に、彼女を迎えたいと、強く思っていた。もし、二人の気持ちが本気だったならば、きっと約束は果たせるだろう。自分たちの気持ちを確かめる期間も兼ねた、名案だった。
(…………) 彼女も私の気持ちが分かったのか、小さく頷いた。
一年という月日は思っている以上に長いものなのかも知れない。
それから私と彼女はいつものように教師と生徒という関係を保ちつづけ、3月になり彼女を含めた5人の問題児たちは、無事に卒業していった。それと同時に私の一年間の清華学園の教員生活も終わった。転任先は、新幹線で三時間かかる、とある県の小さな町の高校。
新たな問題を抱えてのスタート。時間が慌ただしく流れてゆく。彼女に対する気持ちに変わりはなかったが、そんな日々の中で次第に彼女との連絡も疎遠になり、その年は終わった。そして、その翌年も、翌々年も、ただ、過ぎていった……。
目の前の彼女に私は自分の不甲斐なさを強く思い知らされた。彼女はこの6年間、ずっと私との約束を果たすために今日この日、夜遅くまでここに佇んでいたのだ。それを思うと、仕事の忙しさなど言い訳にしか過ぎない。私は約束を破ってしまったのだ。
私は力なくその場に膝を折り、両手をつき深々と頭を下げる。今はそうすることしか思い浮かばなかった。
「センセ……」 彼女は小さな声で言った。言葉遣いこそはさすがに大人になったが、雰囲気はあの頃を失っていない。
「でも、来てくれて……あたしは……」 彼女は決して私を責めようとはしなかった。それが辛かった。私は忘れていたのだから。ここにいるのも、加藤から届いた同窓会への招待状に導かれた訳なのだし。
「それじゃ、どうしてここに来たの?」 彼女の質問に私はどう答えるべきなのだろう。何となくという気分ではなかった。ただ懐かしさが足を運ばせた……そうでもなかった。気づいていたら、ここに立っていた。何かが、私をここへと導いてきた。それでは答えになっていないか。
「約束――――憶えていたんだよ……センセ」
心の奥底で静かに燃えつづけていた彼女への想い。忘れかけていた気持ちは、忘れてはいなかったのか。彼女と離れ、時が経ち、それなりに女性とのつき合いもあったが、結婚に対して消極的だったのは、そうだったからなのか。彼女と交わした約束を果たすことを、ずっと願いつづけてきたのだろうか……。
彼女は手袋を外し、温かな素手で雪に悴む私の手を包み込む。その瞬間、指先から凍えそうな全身に暖かみが走る。彼女は愛おしそうに私の手を両手で包み、息を吹きかける。
「信じてて、正解だったかな……?」 くすと笑う彼女の表情に私の中で何かが急激に膨らんだ。
そして、気がついたとき私は彼女を強く抱きしめていた。
「せ……センセ……」 突然の事に彼女は一瞬抵抗したが、すぐに肩の力を抜く。
「聖美……随分と長く待たせてしまった――――許してくれ……」
私は泣き出しそうだった。それを懸命にこらえながら、震える声でそう言った。
「…………」 彼女は無言で答えてくれた。
そして、ようやく私は言えた。結婚しよう、ずっとそばにいて欲しいと。
見つめあった彼女の瞳は、あの頃のままに澄んでいた。私を思いつづけてきた、愛に満ちた、暖かな色だった。
瞼がゆっくりと下り、冷えた唇が重なったとき、風に舞う雪に乗せて、鈴の音が流れてきた。
「それにしてもクリスマスの日に同窓会とは、加藤も味なことするなあ」
(美夏に言って良かった…)
「え?何だって?」
「あはは、何でもないぜ、せ・ん・せ・い☆」
「おいおい、もうその先生ってのはやめようじゃないか。」
「そう?……じゃあ、哲也さん・・・それとも女らしく、あ・な・たって呼ぼうかな?」
「うわっ、聖美らしくないぞ。普通で行け、普通で」
「そうか、やっぱり?それじゃ、遠慮なく呼び捨てで――――」
私が開けてしまったこの6年間の空白、そして彼女の想い。これからはその分まで、彼女を深く愛し続けよう。寄り添いながら加藤の家に歩き出した私は、彼女の笑顔を見つめながら、そう心に誓ったのだ。