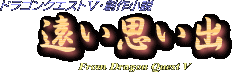
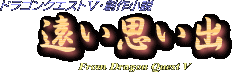
雨が降っていた
忘れられぬ想いに、彼女は一人泣いていた
離れていた時間(とき)が
こんなにも二人を隔てて
もう、あの日の君には帰れない
雨に打たれながら
叫んだ言葉が
空しく響きかき消されて行く
輝いていた幼少の日々は
はるか昔の遠い思い出
大神殿を逃れたリュカは、旧友でキラーパンサーのプックルと再会を果たし、ルラフェンの街を南に下った。
思えば、この十年あまりの間、彼は過酷な苦難を乗り越え、何事にも不屈で、人の心の痛みが自分のことのように感じる、本当の意味の優しさというものを磨き上げていたのかも知れない。
彼は孤高の戦士だった。
かつて偉大なる父パパスがそうであったように、彼もまたそうであった。
伝説の勇者を捜す旅を続けていた父。その遺志を受け継ぎ、彼はひたすら歩き続けていた。
旅路とは、人との出逢い、そして別離が身に染みて感じる。
何気ない邂逅が、それまでの人生を大きく変えることもある。
一人の人間との出逢い。
本当に旅とは不思議なものである。
そして、この街を訪れ、彼はその人生の岐路に立つことになる。
そう、己の伴侶たる女性に巡り会うことになる、一生忘れることの出来ない、通りすがりの街・・・。
季節は春――――
夕暮れにリュカはサラボナの街にたどり着いた。
ポートセルミの帆船借用のためには、サラボナの太守で富豪のルドマン公に面会する必要があった。
途中で立ち寄った宿場町では、ルドマン公の御息女の婿取りの話で持ちきりだったが、彼はそのような話はまるで蚊帳の外だった。
伝説の勇者を捜す旅。
その時は独り身である自分を意識しなかった。
「ピエールたちは馬車で休んでくれるかい?」
スライムナイトのピエールがこくりと頷く。
「はい。そうさせていただきます」
「ごめんな。連れて行きたいのはやまやまなんだけど・・・」
「気にしないで下さい。仕方ありませんから」
魔物使いとして、彼は善心のモンスターを仲間として連れていたが、そのモンスターたちが主人であるリュカと共に街に入ったことはない。世情を考えれば無理もない話だが、彼はその事でいつも心を痛めていた。
やや哀しげな表情で一人街の入り口を過ぎる。
黄昏時の穏やかな風が、ばさばさの髪を靡かせる。
子犬の吠える声に彼は視線を上げた。
純白のふさふさの毛に身を包んだ、可愛らしいプードルが、小走りに彼の元に駆け歩み、彼を中心にして小さな円を描きながら、人懐こそうに見上げ、尻尾を振っている。
「飼い犬らしいな・・・。誰の犬だろ・・・」
リュカはそう呟きながらしゃがんでみた。
すると、プードルは彼の胸に勢い良く飛びかかり、顔を舐めたり身体中を嗅ぎまわしだした。
「あはは・・・やめてくれ、くすぐったい」
擦り切れた革の手袋を外し、リュカがプードルの頭を軽く撫でてやると、プードルはさも気持ちよさそうに双瞼を閉じる。
「さあ、僕はおまえの主人ではないぞ。おまえの主人はどこにいるのかな?」
刹那。
「・・・リリアン・・・リリアンどこ・・・どこにいるの?リリアンッ」
透き通るような玲瓏とした女性の声色が、黄昏の街を吹く微風に乗ってリュカの鼓膜に届く。
彼が声のした方に視線を送ると、暗がりでも見映えする、一人の美しい少女が焦燥の体で近づいてきた。途端。
きゃんきゃん
プードルがひと吠えして彼から離れる。
その甲高い吠え声に、美少女ははっとなって振り向いた。
「り・・・リリアンッ」
少女は胸元で柔らかく握りしめた白い両手を揺らしながら小走りに駆け寄り、愛犬を受け止めた。
純白のドレスが普段着なのか。相当裕福な良家のお嬢様なのかと、彼はふと思ってしまった。
リュカがそっと立ち去ろうとしたとき、リリアンは再び主人の元を飛び出し、リュカの方に駆け寄ってきた。
「あっ・・・だめっ」
「おっと・・・」
リュカが再びリリアンを受け止める。
「こら。せっかくご主人様が迎えに来たのに・・・」
彼がそっとリリアンを抱き上げ、俯きながら少女の方に振り返る。
「ははは。何故かなつかれてしまったみたいです」
そう笑いながら、なかなか離れようとしないリリアンを抱えながら、少女の方に歩み寄る。
「リリアンが私以外の方に懐くなんて・・・・・・あっ、も・・・申し訳ありませんっ・・・リリアンが失礼を」
「い、いえ」
リュカはゆっくりと顔を上げた。同時に、少女も俯いていた顔を上げる。
二人の瞳が合った瞬間、互いにまるで電撃にでも打たれたかのような衝撃が胸を走った。
時間が止まり、互いの意識が瞳の奥に吸い込まれて行く。
短い時間。
現実に戻された二人は自然と頬を染めて目を逸らしていた。リリアンは尻尾を振りながらリュカを見上げている。
「す、すみません。お返しします」
彼が半ば慌てて、少女にリリアンを差し伸べると、少女はややぎこちない仕草でか細い腕に愛犬を受け止めた。
「で、では。私はこれにて・・・」
様にならない会釈を少女に送り、彼は立ち去ろうとした。
「あ、あの・・・」
少女は無意識に彼を呼び止めていた。立ち止まり、俯きながら振り返るリュカ。
「り、リリアンをおさえてくれて、ありがとうございました。その・・・あ、あなたのお名前を・・・教えて下さいませんか。あ、後でお礼がしたいので・・・」
少女は何故か、この青年の事が知りたかった。
初対面の、見知らぬ、それもぼろぼろの服を纏った得体の知らない旅人。
深窓の令嬢ならば、この様ななりをした男など、道端の小石以上に眼中などないように思うはずだった。
だが、少女は是が非でも、この青年の名前が知りたかった。せめて、名前だけでも。
「リュカです」
リュカはそれだけ言うと、もう一度会釈をして歩き去った。
「・・・リュカ・・・」
少女は繰り返した。二度、三度。
彼の名前を繰り返すたびに鼓動が高まって行く。
そして、眠りから覚めたように少女は彼の後を追おうとした。が、その時彼は夕闇の帳の彼方に消えていた。
そう、自分の名を名乗らなかった事への小さな後悔。
リュカは街の小さな酒場へ入った。白い陶磁器のコップに注がれた酒を呷る。
彼の頭には黄昏時に不意に出会った美しい少女のことが妙に焼き付いていた。
ルドマン公に面会し、帆船を借用するという重大な任務さえも霞んでしまうくらい、あの少女のことが気にかかっていた。
何故か判らない。飲みたいわけでもないのに、自然と酒が口に注がれる。だが、なかなか酔えない。
「あなたも、随分と荒れてますね」
隣にいた華奢な若い男に声を掛けられた。
別に荒れているわけじゃない。自然と、自分でも不思議なくらいに酒が入るだけだ。
「あなたのその格好、旅の人と見ますが、何をしにこの街に?」
男の顔は愛想笑いさえ浮かべてはいるが、言葉には明らかに棘があった。まるで、リュカが招かざる客と言わんばかり。
「ルドマン公に面会をしに・・・」
リュカがそう答えると、男は僅かに舌打ちをして、彼から視線を外した。
「あなたも、やっぱりそうなのか」
"やっぱりそうなのか"とはどう言うことだろう。自分と同じく、ポートセルミの帆船を借用したいと申し出ている者は自分だけじゃないと言うことなのだろうか。
「私の知っている範囲だと、あなたで三十人目ですよ。全く・・・フローラも災難だ」
男が漏らしたその名前に、リュカは敏感に反応した。
噂の祠で取りざたされていたルドマン公の御息女フローラが修道院より還俗し、婿取りをするという。
彼にとっては全く興味のなかった話だから、聞き逃していた。まさか自分もそんな話に乗った男たちの一人としてみられているのだろうか。
「僕は、ルドマン公に帆船を借りたいと願い出るために来た者です」
リュカがそう付け加えると、男は怪訝な表情で再び彼を見た。
「帆船?」
リュカは誤解されないように今までの経緯を簡単に男に話した。
今までは自分の経緯など人には話さないようにしてきたが、カボチ村での苦い経験の後から彼の心の中で変化が生まれていた。
自分を語らない、孤高の旅人を気取っていても、意味がないことを感じるようになったというのか。
語ればきりがないほど、彼は起伏の運命をたどっていた。
自分で、自分のことを語り、新たな自分を見つけることが出来るようになった。
「なるほど。あなたも、いろいろ苦労されていますね」
男は空っぽのグラスを手繰り寄せ、酒を注ぐ。
言葉では言わなかったが、"つき合ってやる"という風に容易にとらえることが出来た。
「フローラ目当てじゃないって事がわかれば、何も言うことはないですよ。ちょうど良かった。私も今日は飲みたい気分なんです。おつき合いしますよ。・・・あ、申し遅れました。私はこの街に住む、アンディって言います」
男はリュカのコップに酒を注ぎながらそう言った。リュカもまた、名乗る。
「明日だなあ」
「何が?」
「お前、まさか忘れたっては言わせねえぜ。フローラさんの婿募集の最終日だろうが」
「あっ、忘れてた」
宿のホールで語り合う男達の声が、リュカの耳に否応なく入ってくる。
「お前さんも、連中と同じかい?」
リュカのサインした宿泊用紙を見ながら、宿の主人が言った。
「いや。僕はルドマン公にお願いしたいことがあり、そのために来ただけですから・・・」
「そうか。悪いこと聞いたね。ま、ごゆっくり」
リュカは久しぶりの湯に浸かった。
外の馬車にいる仲間たちを思えば、浮かれる気分にはなれない。いや、それよりも、彼の頭はあの少女のことで一杯だった。他のことを考えようとしても、無意識のうちに彼女のことを考えてしまう。何だろう、このもやもやとした気持ちは。
その晩は疲れもたまっているはずなのに、よく眠れなかった。
翌日、朝食を済ませたリュカは、サラボナ太守ルドマン公の邸宅へと足を運んだ。
朝もまだ早いというのに、そこは多くの男達で埋め尽くされていた。愕然となるリュカ。
そうか、昨日、宿にいた男達が話していたことって・・・。
「おや? あなたは昨日の・・・」
リュカに話しかける若い男の声。
振り返ると、アンディが微笑みながら会釈していた。
「あなたも・・・って言いたいところですが、そうじゃなかったですよね」
アンディは苦笑した。リュカもまた、苦笑する。
「これじゃあ、ルドマン公にお話しできる機会がなさそうですね。出直してきた方がいいかも知れませんよ」
アンディが上目遣いにリュカを見ながら言う。
「対面できなくとも、一度ルドマン公と言う人物、この目で見てみたいと思ってます」
リュカの言葉に、アンディは僅かながら顔を顰めた。
見回すと、集結している男達は、絢爛豪華な宮廷貴族の正装に身を包んだ、いわゆる『貴公子』風情の若者が多い。
まあ、リュカ自身、人のことは言えないが、見るからに怪しい連中もいるようだが。
「こいつらのほとんどは、フローラを愛し、妻とすることが目的の連中じゃあない。ルドマン公の億万の家財と、フローラの花のような身体だけを我が者にしようとしている、欲の固まった連中なんだ」
アンディの囁くような声には怒りが溢れていた。
「絶対、フローラは誰にも渡さない」
やがて、家の使用人らしき男性が門のような玄関から現れた。
「お集まりの皆様、お待たせいたしました。中の方へどうぞ」
各々会話を交わしながら集結していた男達は列をなしてルドマン邸内へと入って行く。
リュカとアンディは一番最後列だった。使用人の呼びかけから実に三十分後にようやく二人はルドマン邸に入ることが出来た。
二百人は余裕で入れるほど広大な大広間はぎっしりと埋め尽くされていた。
中央の奥に据えられた壇上には人はいない。おそらくそこに当主ルドマンが立つのであろう。
間もなく、使用人の甲高い声が空間に響きわたり、騒然に包まれた会場が、綿に水を浸したがごとく静寂した。
「御当主・ルドマン公のお出ましです」
幾重にも連なった奥の扉。
向かって右側の三つ目の扉が開かれ、黒色の正装に身を固めた、凛々しい白髪白髯の男性がゆっくりと壇上に向かった。
「余がサラボナ大公、ロベルト・ルドマンである」
低く嗄れた、それでもよく透る声が厳かに大広間に反響する。
かつて大魔王の脅威から世界を救った伝説の八勇者の一人、トルネコの直孫と言われるルドマン公。
大富豪とは言うものの、実に噂に違わない、威厳満ちあふれ、気品漂う御仁であった。
「こたびは世界中より、我が娘フローラの婿たる男子を募り、こうして数多の壮士たちがここに集いしこと、このルドマン、心強く思うぞ」
リュカは厳しい表情で、ルドマンを食い入るように見ていた。
――――しかし、ここに集まりし者すべてを、フローラの夫と致すことは叶わぬこと。
ましてや、わが家祖以来培ってきた、天空の盾を始めとする当家の億万の家財を受け継ぐ男子は、私利私欲に走る者ではなく、清廉潔白で、強い意志と、何事にも打ち勝つ勇気を備えた者でなければならぬ―――。
その言葉をリュカは聞き逃さなかった。
『天空の盾』――――
父パパスが悲願であった天空四防具の一つの在処が、あまりにもあっさりと、見つけることが出来た。
ルドマンは、そんなリュカの想いを知る由もなく、話を続ける。
「――――そこで、余はそなたらに試練を与えようと思う」
ルドマンの話が続く中で、ぽつりぽつりと、大広間を出て行く者もいた。遊び半分や、冷やかしでやって来ていた連中に違いない。
「この地の何処かに眠ると伝えられている、【炎の指環】並びに【水の指環】――――。この二つを婚姻の証とし、婿と認める。余の思想に叶う者あらば、ここに残るがよい。無理と思うならば、今すぐ立ち去ることだ」
そう言うや否や、続々と集いし婿候補はルドマンにそっぽを向けて退出して行く。
――どこにあるかも知れない指環を探し出せとは・・・
――このご時世に無茶なことをおっしゃる方よ・・・
――何よりも我が命が大切だ。やめだやめだ。
退出して行く男達のぼやきがリュカの耳に次々と届く。
「はっ――――ルドマン公も手厳しい。ふるいをかけて、残ったのは・・・私だけか」
アンディの呟きに、リュカがはっとなって周りを見回す。
あれ程、埋め尽くされていた大広間は、五分も経たないうちに、彼とアンディの二人だけになってしまっていた。
「ほう――――アンディ。そなたもおったのか。ん―――そちらの若者もか」
ルドマンがリュカの方に視線を移す。
「我が条件、果たせる自信があるのだな」
にやりと笑うルドマン。リュカは半ば慌てて跪いた。
「畏れながら――――」
その時、ルドマンが出てきた扉がばたんと大きな音を立てて開く。
「お父様っ。お待ち下さいっ」
その声を聞いた瞬間、リュカは反射的に顔を上げていた。そして、声を失った。
ルドマンの元に駆け寄ってくる美しい少女は、昨夕彼が受け止めたリリアンなる愛犬の飼い主の少女その人だったからだ。
出逢った瞬間に胸に走ったいかずち。あまり眠れなかった、無意識に考えることは、少女のことばかり。
「んっ――――フローラ、何事か。今は大事なる話の最中だぞ」
フローラ・・・そうか。やっぱりというか、彼女がルドマン公の御息女だったのか。
「わかっております。でも――――皆さんにあまり無茶をさせるようなことはお止め下さい――――」
哀願するように、フローラは父にすがっていた。
「何を言うフローラ。これは何も無茶なことではない。そなたの夫となる男が、どれ程の器量を持つ者なのか、推量するための試験なのだ」
フローラは哀しそうな表情で前方に視線を移した。
彼女の瞳に、二人の若者の姿が映る。幼なじみであるアンディと、もう一人――――
彼女もまた、アンディの隣で跪きながら、自分を真っ直ぐと見つめている凛々しい若者に吸い寄せられるように声を失い、止まった。
「あなたは――――リュカ・・・さん?」
思わずそう呟いたフローラ。ルドマンもアンディも、驚いて彼女を見る。
「何だ。そなた、その若者を知っているのか」
ルドマンが憮然と彼女を見る。
「リュカ、どう言うことですか。フローラが何故、あなたの名前を・・・」
アンディの声がやや震えている。
リュカは茫然とし、ルドマンとアンディの声さえも耳に入らなかった。
フローラに吸い込まれて行きそうな感情を強引に振りほどき、毅然とルドマンに向き直った。
「畏れながら、サラボナ太守ルドマン公に、お願いの儀あって参上つかまつりました」
「ん?」
怪訝な視線でリュカを見下ろすルドマン。
「僕はサンタローズ村より、伝説の勇者を求めて旅をしている、リュカと申す者」
リュカは経緯と用件を語った。
いちいち納得するように頷くルドマン。じっとリュカの話に耳を傾け、時折潤んだ瞳を瞬きさせるフローラ。
「――――なるほど。そなたの意向は良く解った。されど、天空の盾は家祖トルネコ公以来千余年に渡り当家に受け継がれた貴重な代物。当家の数多な家宝とはまた別格なるものにて、そう簡単には手渡すわけにはいかぬ」
ルドマンの非常とも言える言葉に、リュカは寂しそうに瞼を閉じて俯いた。
そんな彼の様子を見つめていたフローラが再び父にすがる。
「お父様っ。リュカさんは今まで私たちとは比べものにならないくらい苦労されていらっしゃるのに、何故天空の盾を託されないのですか」
「信じていないわけではない。ただ、何につけ、天空の盾はそう易々と人にくれるものではないと言うことだ。お前の夫となる男のごとく、無欲かつ勇敢な者でなくてはならん。ただの防具ではないわけだからな」
フローラはなおも父を説得してみたが、父は決して翻意しようとはしなかった。
「リュカとやら」
ルドマンの呼びかけに顔を上げるリュカ。
「そなたは、我が娘フローラを如何思うておる?」
唐突な質問だった。皆の驚いた視線がルドマンに注がれる。
「え――――あ、あの・・・」
「お、お父様っ」
みるみるうちに顔が赤くなって行くリュカ。
フローラはおのが紅潮した顔を隠すようにそっぽを向く。
アンディは狼狽して言葉さえ発せない。視線はきょろきょろとリュカとフローラの間を交錯している。
「・・・・・・」
いきなり言われても、返す言葉が見つからない。心のもやもやを、どう口にすればいいのだろう。
「ふっ――――いずれにしても、余が提示した二つの条件。これを満たさねば、そなたの願い、叶えることは出来ぬぞ。アンディ、そなたも同様。フローラが欲しくば、二つの指環を見つけてくることだ」
ルドマンはそう言うと、席を立った。
「あっ、お待ち下さいお父様っ」
足早に退出して行く父の後を慌てて追いかけるフローラ。大広間にはリュカとアンディの二人だけが残された。
「リュカ、あなたは一体どういうおつもりですか」
アンディは険しい表情でリュカを睨む。
「フローラと知り合いだなんて、昨日は一言も言っていなかったじゃありませんか」
動揺のために、口調が荒くなるアンディ。リュカは俯いたまま、言葉を返すことが出来ないでいる。
「フローラの、あなたを見る視線、ただの知り合いとは思えない。あなたも、フローラを見る視線は何かおかしかった。どう言うことですか。あなたとフローラは、どういう関係なのです」
問いつめるアンディ。彼自身、そんな自分が悔しかった。
昨日、ふとしたことから知り合ったリュカ。彼のことは、その経緯以外、何も知らない。そんな彼が、知らぬ間に愛するフローラと何が起きていたのかなどと、思えば思うほど、口にすればするほど、もどかしく、おのが動揺は益々広がってゆく。大人げない、ただ相手を責めるだけの自分が情けない。
「街の入り口で、脱走したあの方の飼い犬を抑え、お礼を言われただけです」
リュカの語る事実でさえ、アンディは信じることは出来なかった。
もしもそうならば、何故、今この二人は熱い視線で見つめ合ったのだろうか。たかがそれだけで、まるで恋する眼差しで互いを見つめることなんてあり得るはずがない。ましてや、自分はフローラの幼なじみだ。彼女のことならば何でも知っている。彼女に限って、見ず知らずの、こんな薄汚れた男に惚れる筈などないと、確信していた。
「隠し事をしないで下さい。本当の目的は・・・フローラなのでしょう」
猜疑心の固まりと化したアンディには、もはやリュカの言葉のすべてが信じられなくなっていた。
そこへ、再び扉が開き、フローラが沈痛の面もちで入ってきた。
「リュカさん・・・アンディ、ごめんなさい。父って頑固ですから」
アンディは反射的にフローラの肩をつかみ、問いつめるように言う。
「フローラッ! 君は彼とどういう関係なんだ。昨日、一体何があったっ!」
驚くフローラ。その澄み切った、美しい瞳を見開き、唖然とアンディを見つめる。
「彼は君の飼っているリリアンが逃げるのを抑えただけだと言っていた。――――本当のことを教えてくれ」
愕然となるフローラ。リュカと目が合うと、リュカがそっと目を伏せる。
「どうしたのアンディ? 本当のことって、リュカさんのおっしゃっている通りよ」
「・・・・・・」
アンディの瞳は悔しさと苛立ちで潤んでいた。もはや愛する人の言葉さえ信じられなくなっていた自分がとても嫌だった。
「――――もういい」
フローラの肩に置かれていた両手を力無く落とす。そしてかすかに震える声で言った。
「私は、炎の指環の在処を知っています――――。二つの指環は、この私が必ず揃えて見せます」
アンディは挑戦的にリュカを睨むと、ゆっくりと大広間を出ていった。
「アンディ・・・・・・」
幼なじみの背中をじっと見つめるフローラ。
アンディが視界から消えると、彼女はゆっくりと振り返り、リュカを見た。互いに無意識に頬が紅潮する。
「大変な旅をなさっていらっしゃるのですね・・・」
「いや――――私よりも、貴女こそ、ご苦労されている。名家の御息女ともなれば、色々と大変ですね」
「あ――――先日は大変失礼いたしました。ご恩を受けたのに、名乗らずに帰ってしまって――――」
「い、いえ。・・・でも、もしかしたら――――って、思っていたんです」
二人は立っていることさえ忘れているかのように、話していた。知らぬ間に、口からは次々と様々な話題が発せられる。自然と、そしてごく普通に二人は会話していた。
どのくらいの時間だろう、二人きりの大広間に、笑い声が反響する。そして――――。
「でも・・・・・・アンディはともかく、まさか、あなたがいらっしゃるなんて、思ってもみませんでした――――」
フローラがふっとリュカから視線を逸らす。
「僕も、まさかあなたがルドマン公の御息女だとは、思ってもみませんでした――――」
リュカも恥ずかしそうに言う。
「あなたを見たとき、何故かとても胸が苦しくなって――――。何て言うか、とても嬉しかったんです」
「僕も、最初はそんな話には興味がないと思っておりました。ですが、今貴女を見た瞬間――――いや、昨夕、街の入り口で貴女を見た瞬間から・・・僕は・・・・・・」
リュカの言葉の後、短い沈黙。互いの鼓動が聞こえそうで恥ずかしい。
「僕も二つの指環、見つけて見せます。そして、必ず、貴女とルドマン公の御前に――――」
今度は真っ直ぐとフローラを見つめる。
彼女もまた、リュカの瞳を見つめる。
二人の脳裏に一瞬、アンディの事が浮かぶ。
「アンディも・・・」
フローラが呟く。リュカが毅然と言う。
「彼とは真剣勝負です」
「・・・・・・」
小さく、彼女が微笑んだ。
リュカは一つ、大きく頭を下げると、ぼろぼろに近いマントを翻して大広間を出ていった。