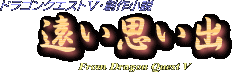
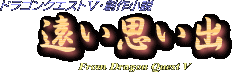
アンディは、サラボナ火山に単身で乗り込み、大怪我を負った。
リュカが炎の指環を手に入れ、アンディを背負いながらサラボナに戻ったのは、一週間後の昼過ぎのことだった。
リュカのおかげで幸い命に別状はなかった。
リュカは炎の指環を携えてルドマン邸に向かった。
使用人に先導されて、彼は応接間に通された。大広間とは格段に小さい、十二畳程度の客間。中央に置かれた濃紺色のソファーには、当主ルドマン公とその妻メアリが満を持して腰掛け、その脇に立っていたフローラは、リュカの姿を見ると、僅かに頬を赤らめて笑顔を輝かせた。
リュカはルドマンに勧められてソファーに座る。そしておもむろに溶岩魔人を倒して得た至宝・炎の指環を、木製のテーブルの上に置いた。
「おおっ、これぞ正しく『炎の指環』。やはりそなたはただ者ではないと思うていたぞ」
「まあ。これが噂に名高い炎の指環ですか」
ルドマンと妻メアリは初めて見る永遠の至宝をまじまじと見ながら感嘆する。
「リュカさん、ご無事で何よりです・・・・・・」
フローラは潤んだ瞳で、無数の傷や火傷を負ったリュカの顔を見つめていた。
「それよりも、太守、フローラさん。アンディさんが・・・」
リュカは事の次第を語った。驚愕する三人。
「な、何と。アンディが単身火山に」
失望のこもった怒りがルドマンの口から漏れる。
「アンディ! なんてことを。」
顔を覆うフローラ。
「す、すみませんっ。私、アンディの所へ行って来ます」
「あ、フローラッ、待ちなさい」
メアリ夫人の制止の言葉も聞かず、フローラは駆け出すように応接間を出て行く。
「あの愚か者め。己を知らずに無謀なことをしおって」
顔を顰めてテーブルを強く叩くルドマン。
「アンディは異常なほど情熱的な面がありますから。きっと、フローラが見ず知らずの男性と結婚することがものすごく嫌だったのでしょう」
メアリ夫人は安堵のため息の後、言った。
「それにつけても、人を心配させるような行動に走る奴だとは思ってもみなかったぞ。内心、余は奴を買っていたのに、失望したわ」
ルドマンの怒りはため息に変わっていた。
「アンディさんは勇敢な方です。僕は彼に対し敬意を表します」
リュカがそう言うと、ルドマン夫妻は微笑んで彼を見た。
「そなたは優しいのう。そなたならば、フローラの夫に相応しい」
「フローラはリュカさん、あなたのことをすごく気に入っているみたいですよ」
「えっ?」
メアリ夫人の言葉に、リュカの静かな表情がやや上気する。
――――実はあの会見の日の前日から、少しフローラの様子がおかしかったの。
何かこう、魔法にでもかけられたかのようにぽーっとして………。食事もあまり喉を通らなかった様子でね。会見の日から、急に元気になったかと思うと、話すことはあなたの事ばかりで……。
リュカの鼓動が次第に高まって行く。無意味なほど、瞬きが激しくなる。こみ上げてくる感情が胸を締めつける。
「リュカ君」
ルドマンの呼びかけにはっと我に返るリュカ。
「君はとても優しい人間のようだから一つ言っておく」
真っ直ぐにルドマンを見るリュカ。
「同情と憐れみ、そして、愛は違うものだと言うことだ」
「・・・・・・」
ルドマンは続ける。
――――君ならきっと、水の指環も見つけだし、我が条件を果たすことが出来るだろう。
君は余が示した、フローラの夫となるべきに相応しい男。・・・だが、それはあくまで、余が決めた尺度に他ならない。
本当の結婚というものは、男女が出逢い、恋をし、愛情を培ってからたどり着く終着点だ。親とはいえ、第三者の立場である余らが決めるものではない。
・・・だが、夫婦とはそのような生半可なものではない。こればかりは一生の問題だ。伴侶として、老い朽ちるまで共に寄り添わねばならない。
余は二つの指環を条件を出したが、そのようなものは正直申して無意味だ。
だが、こればかりは言える。
この条件を果たすが果たすまいが、真にフローラを愛する者であれば、余は結婚を認めるつもりでいたのだ。
だが、アンディはどうか。一時の憤懣に駆られ、己を省みず無謀にも街を飛び出し、挙げ句の果てに大怪我まで負うとは・・・。己を知らぬ者には、他人を幸福に出来ようはずはない。
『愛があればたとえ火の中』とは言うが、そのようなものは詭弁に過ぎない。己を知る者こそが己の伴侶を幸福に出来ると思うておる。
一時的な感情では幸福にはなれぬ・・・。
リュカには、ルドマンの示唆している意味がおぼろげながら感じ取ることが出来た。
それは彼自身、正直心の中で、フローラはアンディに相応しいのではないか。また、例えもう一つ、水の指環を見つけだしたとしても、フローラはアンディの妻となるべきだという思いを払拭する言葉でもあった。そして、おのが思いを呼び起こした言葉でもあった。
毅然とした視線で、ルドマン夫妻を見る。
「太守。夫人。・・・今の話を聞き、ようやく気づきました。僕は・・・フローラさんを幸福にしたい」
その言葉に夫妻は微笑んだ。
――――僕もあの日、街の入り口でフローラさんを見かけたときから、何故か胸が苦しくて、太守への用件さえも忘れかけるほどでした。
それが何なのかという事に気がつかず、ただ言われるがまま炎の指環を見つけて参りましたが、ようやく答えが見つかりました。
・・・僕は、フローラさんを愛してしまったんです。
誰よりも、何よりも、彼女の事が・・・。
リュカの声は震えてさえいるが、毅然としていた。
「水の指環、必ず見つけだしてご覧に入れます」
夫妻は何も言わず、微笑んでいた。
リュカはルドマンが用意した帆船で、内海を北上した。
サラボナ湾とルラフェン海を繋ぐ水門が閉ざされ、リュカは水門を管理しているという山奥の村へと足を運んだ。
「水門管理してんのは、村の一番奥にあるでっけえ家だべさ」
村人に教えられ、リュカはその家に向かった。
途中、ふと道端に目が行ったリュカは、思わずぴたりと足を止めた。
数体の墓標が並ぶ。
その一つに手を合わせている、三つ編みにした金髪の女性の後ろ姿。
リュカは何故かこの女性に、無性に懐かしいものを感じた。
そして自然と、そうするのが当たり前のように声を掛けてみる。
「あの・・・・・・」
しかし、その女性はリュカの声に気づかず、一心に墓標に祈りを捧げている。
(邪魔しちゃあ悪いか)
彼は気づかれないようにそっとその場を離れた。
二度、三度振り返ってみたが、その女性の顔は墓標に遮られて見えなかった。
村の奥にあるその家は、高床式の木造平屋建てであった。木々の新しさから、そんなに古い家ではないことが容易に推察できる。
「すみません。サラボナ太守ルドマン公の使いとしてやって来た者ですが」
リュカが扉をノックする。しかし、誰も出てきそうにない。
「おかしいなあ。誰もいないのかな?」
再び、ノックする。しかし、やはり誰も出てきそうもない。
(仕方ない。明日また出直してくるか)
そう諦めて戻ろうとしたときだった。
「あの・・・何か・・・」
少女のように澄んだ、鈴の音の如き声がした。
リュカが顔を上げると、そこに花籠を携えた一人の美しい少女――――。
墓標に祈りを捧げていた、あの三つ編みの少女だった。
一瞬、声を失うリュカ。
その秋の晴れわたる空のように澄んだ瞳は、不安げにリュカを見つめている。
「あっ、すみません・・・」
リュカが短い階段を下りて少女の脇に立つ。
少女はじっと彼を見つめていた。
そして、彼女が何かに気づくまで、そう時間はかからなかった。
「・・・もしかして・・・・・・もしかして・・・・・・」
「は?」
リュカを見ながら呟く少女。不思議そうに彼女を見る。
「・・・・・・リュカ? リュカじゃない?」
思い出したかのように、少女の不安そうな表情は、途端に満面の笑顔に変わる。
「そう・・・ですが」
「あぁ! やっぱりそうなのね」
花籠を落とし、少女はいきなり彼に抱きついてきた。
愕然となるリュカ。やり場のない両手が空を舞う。
「あ・・・あの・・・」
「リュカ――――私よ・・・・・・ビアンカ。小さい頃、あなたとよく遊んでいた、ダンカンの娘のビアンカ。忘れちゃった?」
リュカはゆっくりと記憶の糸を辿った。
十年以上も前・・・。
そう、偉大なる父パパスに手を引かれて訪れたアルカパの街。
そこで彼は一人の少女に出逢った。
ビアンカと名乗った、二歳年上のその少女は、彼に対して、やけに姉貴ぶっている変わった少女だった。
レヌール城に出没するという幽霊の噂を聞くや否や、深夜にたたき起こされ、強引に幽霊退治に駆り出されたこともあった。
当時、まだベビーパンサーで、街の悪ガキ達に虐められていたプックルを救うためだは言うものの、年端の行かない少女が、夜遅く幽霊城に乗り込むその胆力は、少年にとってはさも恐ろしくさえ感じていたものだ。
でも、別れはすぐにやってきた。
彼女の父ダンカン夫妻が、アルカパの宿を引き払って隠遁するのに、彼女も同行した。
惜別だった。
別れたくない、一緒にいたいと泣いていたのは、不格好にも彼自身だった。
そんな短い思い出。
十余年の年月が経ち、それは彼の心の引き出しに、セピア色の思い出となっていた。
「思い出したよ。そうだ、ビアンカ。ビアンカだ。さっき、墓標に手を合わせていた君を見たとき、何か懐かしい感じがしたんだけど・・・そうか。ビアンカだったんだ」
さっと彼から身を離して前に立ち、彼女は微笑んだ。
「リュカ――――立派になったね。あの頃とは大違い」
「ビアンカ・・・・・・君も随分と綺麗になったよ。あの頃とはまるで別人だね」
幼なじみは今になっても昔と変わらず、互いの頬に手を当てて懐古する。
「それに、すごく逞しくなったわ。背だって、あの頃は私の方が頭一つ分高かったのに、今はほら――――」
彼女がぴたりとリュカに寄り添うように立つ。
「私の背丈、あなたの胸あたりしかない・・・・・・」
リュカを見上げて、その瞳をじっと見つめる。
刹那の沈黙。リュカは不意に瞳をそらした。
自分をじっと見つめる彼女を、意識してしまった。
あの頃から、『幼なじみ』として、『姉』として思っていた彼女を、ふと過ぎる思い、『一人の女性』。
突然、彼女の手が鳴った。驚くリュカ。
「ねえ、家に寄って。せっかく十年振りに再会したのよ。お父さん、大喜びするわ。ね、いいでしょ?」
この強引さは昔と変わらない。リュカは笑って頷いた。
「そうと決まれば、今日の夕食、奮発しなきゃね。入ってて。私、買い出ししてくるから」
そう言うと、彼女は扉の鍵を開けて花籠を拾うと、細く長い脚を舞うようにして、村の方へ行ってしまった。
「素早さもかわらないなあ・・・」
家に入ると、暖炉の火が小さく音を立てていた。
春とはいえ、やはり山は冷え込むらしい。暖炉は夏場まで欠かさないのか。
「・・・ビアンカ。帰ったのか?」
奥の扉から嗄れた男の声がする。
「話し声がしたようだが、誰かお客さんか」
やがて、扉が開き、無精ひげを蓄えた初老の男がふらつきながら現れた。
男はリュカを見るや否や、驚愕したように声を荒げた。
「お・・・お前は誰じゃ」
目の前に立つ不審な男に腰が抜けそうになる。リュカは慌てて支える。
「な、何をするのじゃ! お前は・・・」
「ダンカンさんですね?」
リュカがそう言うと、ダンカンは怪訝な眼差しで彼を見る。
「僕です。リュカです。パパスの息子の・・・リュカです。」
そう名乗ると、しばらく考え込んでいたダンカンの表情がみるみるうちにゆるんで行く。
「パパスの息子・・・リュカ? ・・・おお、思い出したぞ。お前さん、あの時の・・・」
ダンカンがリュカに支えられながら立ち上がると、顔をくしゃくしゃにしながらリュカの頬に手を当てる。
「おお・・・リュカか。しばし見えぬうちに・・・随分と大きくなりおって・・・」
「お懐かしゅうございます。あの時は大変、お世話になりました」
深々と頭を下げるリュカ。ダンカンは鼻水を啜りながら、何度もリュカの両肩を叩く。
「リュカよ・・・わしゃあ心配しておったぞ。あれから十年も、なんも音沙汰なく・・・もしや旅路の途中で・・・などとな」
「すみませんでした。この十年、色々なことがありすぎまして・・・」
「ところで・・・パパスは・・・お前さんの父上はどこじゃ? 達者なのか?」
「それが・・・」
リュカは父パパスの死、そして自分の経緯を語った。
「そうか・・・それはひどく苦労してこられたの・・・」
ダンカンはリュカを食卓に導き、椅子に腰掛けると、自分たちの経緯も語った。
アルカパの宿を人手に渡し、この地に住むようになったのはいいが、間もなく、病気一つもしなかった、最愛の妻でビアンカの母マルガレータが突然病死。
それ以来、心労の続いたダンカンが倒れたのは三年前。
あの頃は色つやも良く、やや肥り気味だった身体も、みるみるうちに痩せた。
いくらか体調も回復したが、それでもまだ寝たり起きたりの状態が続いているという。
マルガレータ死後、家事はビアンカが一切賄っていた。
毎日、母の墓前の花を絶やさず、妙齢になり、更に美しくなったビアンカ。
買い物のために街に出れば、若い男達が言い寄ってくるだろう。しかし、彼女は誰にも見向きもせず、ただひたむきに家事をしていた。
「リュカよ」
「はい」
「実を言うとな、ビアンカは儂の本当の娘ではないんじゃ」
「!」
愕然となるリュカ。思いもよらぬダンカンの告白に、瞬きすら忘れる。
「二十年前、儂と亡き妻がとある森で拾った、捨て子だったんじゃよ」
ダンカンは語った。
夫妻が宿で使う薬草採りにアルカパ外れの森の中を訪れたとき、不意に差し込む明るい光があった。
そこへ行くと光に包まれ、眠る一人の稚児。
子供がなかった夫妻は、その稚児を自分たちの子として育てようと決めた。そっと拾い上げると、どこからともなく声が聞こえた。
『かつて天空の勇者に道を示した、ブランカの末裔に託す』
後から知ったことだが、ダンカンは古のブランカ王室の末裔だった。
言い伝えによれば、かつて大魔王の脅威から世界を救った、天空の勇者が初めて訪れた地上の国ブランカ。
当時の王はみすぼらしい姿の少年の資質を見抜き、道を示したという。
「その事をあの娘は知らない。いや、うすうす感じてはいると思うが、あえて口に出さない、健気な娘なんじゃ。それを思うと不憫でな。何だかんだと言っているうちに、あの娘ももう二十歳じゃ。儂のことより、おのが幸せを望んでほしゅうてな・・・」
ダンカンの声は既に嗚咽が入っていた。
「リュカよ。儂の願い、聞いてくれんかの・・・」
「・・・・・・」
「あの娘を・・・ビアンカをもろうて欲しい・・・」
その言葉を聞いた瞬間、リュカの心に激痛が走った。
運命とは何と酷いのだろうか。神は人に一体幾重も試練を与えるのだろうか。
水の指環を探すため、水門を開けてもらうために訪れたこの小さな村であまりにも偶然に再会してしまった幼なじみ。そして、ダンカンから語られるこの空白の十年。
その時、玄関の扉が開き、野菜や果物を山のように抱えたビアンカがかすかに息を切らしながら入ってきた。
「あっ――――お父さんただいま。身体、大丈夫?」
慌てて裾で顔をこすり、笑みを浮かべるダンカン。
「おおビアンカ。ほれ、リュカだぞ。お前の幼なじみの、リュカが来ておるぞ」
「うふふ。わかってる。だから今日はごちそう作るために、いっぱい買い物して来ちゃった。・・・お父さん、リュカ。ちょっと待っててね。今日はうんと腕によりをかけるから」
何か嬉しそうに台所に立つビアンカ。まな板を打つ包丁に合わせて鼻歌を歌う。
その背中を眺めながら、ダンカンもリュカも言葉を発しなかった。
やがてダンカンは少し休むと言い、寝室へ戻っていった。
「美味いっ! とっても美味しいよ、ビアンカ。」
リュカはビアンカ手製の料理を口に運びながら、一々感嘆していた。
テーブルに両肘を置き、手のひらに顔を乗せて、そんなリュカを微笑みながら見つめるビアンカ。
「ねえ、リュカ、一つ訊いてもいい?」
「ん、何?」
「あなた・・・どうしてこの村に来たの? あなたの様子だと、私たちを訪ねてきた風でもなさそうだし・・・」
その質問にリュカは気づいたようにナイフとフォークを動かす手を止める。
「そうだ。僕は水門を開けてもらうために、ここに来たんだ」
「水門? ああ。あの水門ね。・・・でも、何故?」
ビアンカが不思議そうにリュカを見る。
「それは・・・・・・」
リュカは言いかけて止まった。
実にタイミングの悪い状況だった。ダンカンから言われた後、まさかフローラと結婚するために、水の指環を探す旅をしているなどと、そう軽々しく言えようはずがなかった。
「それは・・・何?」
「天空の盾っていう伝説の防具が、ルラフェン海の方にあるって聞いたから・・・それを探すために」
咄嗟についてしまった嘘。だが、ビアンカはすぐにそれを嘘と見破っていた。
「リュカ、正直に言って」
彼女に隠し通すことは不可能と悟ったリュカは、正直にその経緯を語った。
「そう・・・・・・」
寂しそうな表情を見せたビアンカ。しかし、すぐに笑顔に戻る。
「よかったじゃない。おめでとう、リュカ」
その笑顔が無理に作ったものであることは、容易に察することが出来た。
「そう言うことなら、喜んで協力するわ。だって、あなたの幸福のためだもん」
まるで自分に言い聞かせるように、彼女は言った。リュカは何も言えない。
「水門を開ける代わりに、一つ条件があるの。聞いてくれる?」
「何?」
「その指環探すの、私も連れていって」
リュカは驚いた。
「し、しかし・・・」
「イヤだって言うなら、水門は開けてあげない」
彼に選択の余地はなさそうだった。
戸惑いながらも承諾すると、彼女は子供のようにはしゃぎ、喜んだ。
ルラフェン海に注ぐ大河の上流に、洞窟があるという。
そこに『水の指環』がある可能性が高いと、とあるところで聞いたリュカ達は、十日かけてその洞窟にたどり着いた。
船を下り、洞窟の入り口に立ったリュカとビアンカ。不意に、彼女が声をかける。
「ねえリュカ、思い出さない?」
「何を?」
「昔、プックルを助けるために、レヌール城でお化け退治をしたときのこと」
記憶の片隅におぼろげに残るセピア色の出来事。
暗い夜道を二人、半ば怯えながら廃城へと向かう。そして城主夫妻の苦悩・・・安らぎ・・・。それは、遠き日の思い出。
「ああ、覚えてるさ。あの時は災難だったよ。人が寝ているのを強引にたたき起こされて・・・」
「お昼に寝て、真夜中に起き出して・・・」
「そうだよ。あの時は装備も弱くて、お金貯めるために、何日も吸血鬼のような生活だった」
「ふふ・・・あなたって、大きなあくびをしながら戦って。寝惚けて、何度危ない目にあったか」
「よほど眠かったんだろうな」
くくと笑うリュカ。
「でも、ドキドキしたよね。・・・今から思うと、ホントに小さな冒険だったけど、何か、すごく楽しかった気がするの」
「ああ。そうかも知れない・・・・・・」
「何か、思い出すなあ。あの頃」
「・・・・・・」
「ねえリュカ? ・・・あなたと別れるとき、私と交わした約束、憶えているかしら」
彼女の言葉に、彼は不覚にも、答えが見つからなかった。
「ふふっ。憶えているわけないよね」
「ご・・・ごめん」
平謝りするその姿は、不格好であった。
「いいの・・・。私、こう言ったわ。《いつかまた、一緒に冒険しましょう》って」
そう言われてようやく思い出した。
彼にとっては、何気ない彼女の言葉だった。
だが、その言葉が、彼女にとって、今まで支えにしてきたであろう、大事な言葉だった。
リュカは、何よりも彼女の一番大切なものを忘れていたのかも知れない。
「約束、果たせたね。こうして、あなたとまた冒険が出来たことで・・・」
リュカは何も言えなかった。
今、何を言っても下手なフォローでしかならないと思った。
僅かながら、彼女の肩は震えていた。
強かな性格。
しかし、もろい面も持つ彼女。
涙を怺えているのだろう。それを隠すかのように、必死で笑顔を見せる彼女が、とても小さく見える。
小さくて、もろくて、今にも手折れそうだ。
思い切り抱きしめてあげたい衝動に駆られる。しかし、今のリュカに、それは出来なかった。
止めどなく落ちる滝の音が、彼女の小さな涙を隠してくれていた。
「いこっ、リュカ。早く見つけて、太守様に届けないと」
そして、彼女はいつもの明るい声でリュカの手を取り、先に立って洞窟に足を踏み入れていった。
水の指環は、二人の時間を与えまいとばかりに、呆気なく見つかった・・・。
「これで堂々と胸を張ってサラボナに帰れるね」
「あ、ああ。そうだね」
「なあに? せっかく見つかったのに、そんな冴えない表情して。素直に喜んで」
しかし、リュカは素直に喜べなかった。
「ねえ、私もサラボナに行っていい?」
「えっ・・・?」
「あなたとフローラさんの結婚式よ。幼なじみとして、出席するのは当然でしょ?」
「そ、それはそうだけど・・・」
「決まりね。じゃあ、このままサラボナに直行しましょう」
リュカに有無も言わせず、結局彼女もサラボナに行くこととなった。
無論、彼女自身、波乱に身を投ずる覚悟は、とうに出来ていた。