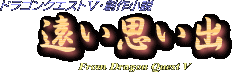
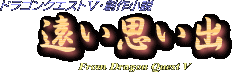
リュカが帆船でサラボナを発ってから、二十日後に再びサラボナに帰還した。
船を下り、少し後からビアンカがそれに続く。彼はようやく見慣れた風景。彼女にとっても、幾度か訪れている街。
おもむろに二人はルドマン邸に向かった。
玄関先に、空色のドレスを着た美しい少女がプードル犬をあやしていた。フローラであった。
彼女はリュカの気配を感じ、振り返る。
「あっ――――リュカさ・・・・・・」
笑顔が一瞬のうちに曇る。
ふと、リュカの背後に目を配る。
そこに立つ、見知らぬ金髪の美しい女性。
じっと自分を見ている。二人の美女の視線間、火花が散る。
「あの・・・・・・そちらの方は?」
フローラが不安まじりに尋ねる。
「は、初めましてっ。私はリュカの幼なじみでビアンカって言います」
慌てるように頭を下げ、名乗るビアンカ。
僅かながら眉をしかめたように見えたフローラ。だが、すぐに微笑みに変える。
「まあ。リュカさんの・・・。初めまして、太守ルドマンの娘フローラです」
しかし、何故かぎこちない雰囲気が二人の間を漂う。
「フローラさん」
リュカが割り込むように話しかける。
「あ、待って下さい。お父様に知らせて参りますから・・・どうぞ、お入りになって」
フローラが二人を邸内に導く。
リュカの両脇に二人の美少女が並ぶ。『両手に花』と言えば聞こえはいいのだろうが、今は取り分けそんな浮かれたことを言っている状況ではなかった。
「ねえリュカ。やっぱり、私がいちゃまずかった?」
そっとリュカの耳元で囁くビアンカ。嘆きまじりのため息をつくリュカ。
「今さら何を言ってんだよ。それを覚悟で来たんじゃないか」
リュカは足を早めて前に出、ビアンカはリュカの後をつくように応接間に向かった。
フローラは慌ててリュカの横につくが、気になるのか何度も視線をビアンカの方に送る。
応接間の前でリュカとビアンカが立ち止まる。
「すぐに来ると思います。お待ち下さい」
そう言い、フローラは先に応接間に入っていった。
「綺麗な人ね」
棘がかかった声で呟くビアンカ。
「あなたにぴったりな女性だと思うわ」
「そうかな」
肯定とも疑問とも判断し難い返事をするリュカ。
「あの娘の目、あなたを好いている目をしてた。そしてあなたも・・・」
その言葉には返事をしない。
彼女もこれ以上、言葉を発することはしなかった。聞きたいことは山ほどあるのに、これ以上口を開くと、妬ましい女だと思われてしまうかも知れない。それがいやだった。
やがて応接間の扉が開き、フローラが顔を覗かせた。
「リュカさん、ビアンカさん。どうぞ」
リュカがゆっくりと入る。ビアンカも後からおそるおそると入った。
ルドマン夫妻は立ってリュカを出迎えていた。リュカの凱旋を、満面の笑顔で祝福するかのように。
「ただいま、帰参いたしました。・・・太守、夫人。水の指環はここに」
リュカが水の宝石を差し出すと、夫妻はまるで幼き子供のような歓喜にうち震えた。
まるで自分の子供のように何度もリュカの頭を撫で、肩を抱き、接吻する。照れて顔が紅潮するリュカ。胸のあたりで両手を組み、仄かに頬を染めるフローラ。眩しそうにリュカを見るビアンカ。
ようやく興奮が落ち着いたとき、ルドマンはビアンカに気づいた。
「おや? そちらの美しい娘さんはどちらかね」
我に返ったように瞳を見開くビアンカ。
「僕の幼なじみで、ビアンカと申します。こたび、水の指環の捜索に協力してくれました」
リュカが紹介すると、彼女はぺこりと頭を下げる。
「何と、そうであったか。いや、それはそれはようおいでくだされた。余はロベルト・ルドマン。そしてこれは家内のメアリ。そして娘のフローラじゃ」
笑顔で家族の紹介をするルドマン。
幸福そうなその雰囲気に、ビアンカはやや寂しさを感じた。
ルドマン夫妻は祝宴を開き、フローラの夫となるリュカとビアンカをもてなした。
二人にとっては初めて見る豪華な料理に躊躇しながらも、ワインを飲み、他愛もない雑談に笑いを交わし、ビアンカは最初に抱いていた不安は、自然と隠れ見えなくなっていた感じがしていた。
しかし、ふとルドマンが漏らした一言に、隠れていた不安は再びわき起こった。
「ビアンカ殿は、リュカ君の事をどう思っているのかね」
「えっ・・・・・・」
驚いたビアンカに、リュカとフローラの視線が向けられる。
歓談は止み、食器の音も止まる。皆、自然とビアンカの答えを待ち、沈黙する。
「私は・・・・・・」
答えがつまる。
冗談まじりで即答出来れば、それでいいはずだった。
だが、彼女は答えが出ず、いたずらに間を空ける。
リュカの表情が自然と困惑色に染まる。フローラも、穏やかな表情が次第に険しさを帯びてくる。
「ただの幼なじみだと思ってます」
ようやくそう答えたが、タイミングが悪かったのか、夫妻の反応はやや遅かった。
その間が、夫妻やリュカ達に余計な思考時間を与えてしまったのか。たかが一分の間とはいえ、色々な考えを過ぎらせるには十分に余裕がある時間だ。
「・・・そうか。幼なじみのう・・・」
ふと、ルドマンの顔が曇る。メアリ夫人は苦笑気味に微笑んでいる。
「おお、そうであった。フローラ、アンディの様子はいかがか」
ルドマンは話題を変えようとしたが、思いついたのはアンディの事。幼なじみがキーワードになってか、リュカにとっては恋敵である男の名を出してしまった。
「アンディなら、もう大丈夫だと思いますわよ。フローラが介抱してくれていたみたいですから、治癒に拍車がかかっていたみたいですから」
メアリ夫人が代弁する。
フローラはどうやら、あの後すぐにアンディ宅へ飛び、彼を誠心誠意介抱していたらしい。
ふと、リュカの脳裏に一縷の不安が過ぎる。
「私のために危険な火山まで行ってくれたのです。それくらいのことは」
フローラはきっぱりと言った。
決して後ろめたいことはないと、その瞳は言っていた。
ルドマンの場の悪い質問から、その場の空気が重みを帯びている感じがする。リュカは、更に酒を入れてもなぜか酔えなかった。
祝宴が終わりの様相を呈してきたとき、メアリ夫人が口を開いた。
「ビアンカさん」
「は、はい」
「せっかくいらしてくれたんですから、今日はここに泊まって行かれたらいかがかしら」
「え、あ・・・で、でも・・・」
不意な夫人の厚意に戸惑うビアンカ。
「いいじゃない。ね、フローラ。いいわよね」
「ええ。ぜひそうして下さいませ」
フローラは微笑んでいた。ふとリュカに目を配ると、彼もまた微笑みながら頷いていた。
ビアンカはその日、ルドマン邸に泊まることになった。
フローラの厚意で、彼女の部屋で共に休むこととなり、リュカが宿屋に戻った後、二人はフローラの部屋でくつろいでいた。
夜も更け、月は中点にさしかかる頃、フローラは部屋の灯りを消し、そっとカーテンを開けた。
月の淡く幻想的な皎(しろ)い光が窓越しに部屋全体を照らす。
窓を開けると、ひやりとした清々しい風が入り、大きく息を吸うと、とても新鮮な香りがする。
「私、八歳の頃から修道院にいたから、年の近い友人が少ないの・・・」
月を見上げていたフローラがそう呟いた。
ビアンカがフローラの背中を見つめる。
「だから、あなたと親しくなることが本当はとてもうれしかったのに・・・・・・。ビアンカさん。ごめんなさい。私、最初にあなたを見たとき、いい感情を抱いていなかったわ」
「・・・・・・」
「リュカさんがあなたと一緒にいるところを見たとき、なぜかドキドキしてしまって・・・。この二十日間、アンディを看病していてもリュカさんのことばかり考えていたわ。だから・・・・・・」
そっとフローラの横に立ち、共に月を見上げるビアンカ。彼女にはフローラの気持ちは良く解る。
「ごめんなさい。私、そう思われることを覚悟で、気の進まなかったリュカを押し切って来たから。・・・でも、安心して。私、別にリュカのことは何とも思っていないから。本当よ」
「・・・・・・」
フローラは何も答えない。
「フローラさん、あなたに聞いてもらいたいことがあるの」
「えっ?」
「ちょっとした、身の上話よ・・・」
ビアンカは大きく夜の空気に大きく深呼吸をする。彼女の言葉を待つフローラ。
「――――私には両親がいたわ。母は三年前に亡くなったけどね――――。でも、血の繋がった本当の親じゃないの」
愕然となるフローラ。
「お父さんも、お母さんも何も言わないけど、うすうす気づいていたわ。"感"って言うのかな。それでやっぱりって思ったのが、お父さんとリュカの話を聞いたとき・・・」
彼女はあの時、玄関越しに父ダンカンとリュカの会話を聞いていたのだった。
買い出しから戻り、玄関を開けようとして手が止まる。
聞こえてくる言葉は、彼女自身の秘められた幼い頃の事実。
彼女はすべてを知ると、心の中で泣き出した。
だが、強かな性格の彼女は何も知らない素振りを見せ続けていた。
「・・・・・・だから、あなたの気持ちは良く解る。あなたが・・・リュカを好きになった気持ちも・・・・・・」
「ビアンカさん・・・やはり本当は・・・」
ビアンカは小さく首を横に振った。
「私は気持ちを偽ってなんかいない。あなたこそ、自分の気持ちに嘘をついてはいけないわ」
とはいうものの、ビアンカ自身、強がっていた。フローラもまた、自分の心に問い質していた。
ビアンカに比べて、自分は恵まれた環境に育った。
親元を離れ、修道院にいたとはいえ、ビアンカの苦労に比べると、全然大したことじゃない。
結婚のため修道院から戻り、幾日も経たないうちにリュカに出逢い、彼を一目見たときから、惹かれていく自分を感じていた。
そしてビアンカとも出逢い、彼女もリュカのことを好きなのだろうと確信を抱いたのも、一目見たときだった。
彼女の話を聞き、一瞬、リュカを諦めようと思っていたが、どうしても出来なかった。そう思ったのは、ただの同情に過ぎないのではないだろうか、と。
(私はリュカさんが好き――――この気持ち、隠すなんて出来ない――――)
それから二人は声を発することなく、しばらくの間、皎い月を見つめていた。
翌日、リュカはルドマンに呼ばれた。その場には夫人も、二人の美少女もいない。
「リュカ君。結婚式の準備は既に整えてある。頼んでおいたシルクのヴェールも今日中には届くだろう。気が早いと言われそうだが、明日にでも式を挙げたいと思うておる」
リュカは覚悟を決めていたので驚きはしなかった。
「フローラの夫となる決意は出来たかね」
「・・・・・・」
リュカは言葉を詰まらせた。当然のように頷くルドマン。
「迷うておるようだな。フローラか、あのビアンカという娘か」
図星であった。ルドマンはしばらく考えてから言った。
――――良かろう。
今日一日、ゆるりと考えてみるがよい。
おのが伴侶と成す女性は、迷ったままでは後悔や不幸を招く。余が口出すべき問題ではないからな。
・・・・・・式は明日、正午より街の大聖堂で執り行う。それまで、ゆっくりと考えるがよい。明日、大広間にてフローラかビアンカ殿か、どちらかを選ぶこととする。
リュカは愕然となってルドマンを見た。
「太守、それはあまりにも屈辱的な・・・」
どちらかが振られる無様さを、人前で曝すようなことをしようとしているルドマンの発言に、彼は反発した。
「二人には既に伝え、了承した。リュカ君、君こそ迷いを断ち切り、本当の気持ちを伝えることだ。生半可な気持ちでは、どちらとも傷つけることになるからな」
そう叱咤した後、優しい口調で言った。
「君は二つの指環を見つけだしてきてくれた。私としてはそれだけで君を気に入っている。家宝の盾は君に託すと決めてある。それは何も案じることはない。後は、君の本心を明日、見せてくれればいい」
そう言うと、ルドマンは立ち去った。
後は自分自身の問題。リュカは誰もいなくなった応接間でしばらく考えていた。当然、答えなど早々見出せるはずがなかった。
じっとしていても始まらないと感じ、彼は街に出た。
サラボナの街は明日の結婚式のことで盛り上がっていた。リュカを見る人々が交わす言葉。
「あの男がフローラさんの婿になるってさ」
「そう言えばあの人、金髪の美人連れて来てたわよ。一体誰かしら?」
「何か、明日にフローラさんか、その金髪の美人か、どちらかを選んでから式に出るっていう話だぜ」
「ひゃあ! 贅沢だなそりゃあ。じゃあ、何かい? 二人の絶世の美女は、どちらかが必ず振られるって事?」
「ま、そういうこっちゃな」
「うう・・・そんなうらやましいことがあっていいものなのかよ」
『贅沢』とか、『うらやましい』なんて、そんな問題ではない。
リュカは冴えない表情で宛てもなく街を歩いていた。
彼らの心情を何も知らない、街の人々の喧噪は耳に入らない。
無意味に時間が過ぎて行く。
人生の岐路。
一度進めば、二度と引き返すことは許されない。
ただ、時間は過ぎる。
彷徨う少年の心など、まるで知らぬ振り・・・・・・。
そして、心決まらぬまま、夜の帳が完全に街を包んだ。日中薄曇りだった空。星や月は見えない。
リュカはまだ迷っていた。
心の中で二人の自分が戦う。決着がつかないもどかしさ。眠ることが出来ない。
深夜、彼は宿を出、再び街に彷徨い出た。
晩春なのにひやりとする風。
日中の喧噪は既に止み、家々の灯りも消えて、さながら幽寂な闇の世界。
夏を予感する虫の音が、微かに風に乗って聴こえてくる。それが些少なる落ち着きを与えてくれる。
ふとルドマン邸から漏れている淡い黄色の光。
誘われるが如く、彼の足は向かっていた。
窓に佇む一人の金髪の美少女、ビアンカ。そこはルドマン邸の別館。
「ビアンカ・・・・・」
憂い漂う表情をした彼女の横顔は、思わず抱きしめたくなるほど、切なく、美しく、可憐だった。
無意識に声を掛けるリュカ。
「あ・・・リュカ」
彼の方を向き、寂しそうに微笑む。
角燈の揺れる黄色の灯りに照らされた彼女の澄んだ瞳は、光のせいなのか、潤んだように見える。
「何を考えてたんだい?」
明らかに野暮な問いかけだった。
「ううん、何も・・・・・・ただちょっとね・・・眠れないだけ」
わずかに瞳を逸らし、小さなため息を漏らすビアンカ。
「リュカ、明日よ、結婚式。早く休まないと・・・・・・。寝不足の花婿なんて格好悪いわ」
「眠れないんだ。僕も・・・・・・」
じっと彼女を見つめる。
彼女は目を合わそうとしない。合わしてしまうと、涙がこぼれ落ちてしまいそうな気がしたからだ。
「どうして眠れないの? ・・・ははぁ、フローラさんのこと考えてうきうきして眠れないのね。ダメよ、ちゃんと眠らないと」
「そんなんじゃないよ。その・・・・・・」
自然と声が荒くなる。次の言葉をじっと待つビアンカ。
「・・・迷ってるんだ。正直言うとね・・・・・・」
リュカは力無く呟き、小さく項垂れる。
「・・・何よ。今さら、何を迷ってるって言うの? フローラさんと一緒になるんでしょ?」
わざと突っぱねる様な口調になるビアンカ。
「・・・・・・」
困惑した表情のリュカ。二人の女性の間で揺れ動く心。
そんな顔を見つめていた彼女は、これ以上彼を突き放す様な言動は出来ようはずがなかった。
「・・・入って。鍵は開いているわ」
何故、鍵を掛けなかったのだろう。ただの不用心か。
いや、もしかすると、リュカが忍んでくるかも知れない。自分を求めるなら抵抗はしない・・・。そんなよこしまな期待が、心の中にあったのだろうか。正直、彼女自身、解らなかった。
リュカは言われるがまま、扉を開けて部屋に入った。
部屋の中は薄暗い。だが、その淡い光の中で、ビアンカの美しさはより一層、引き立てていた。
風呂上がりだろうと思わせる、黒いタンクトップに明るい黄土色のショートパンツ姿。いつも三つ編みにしている金色の髪は解かれて、腰や胸の辺りまで垂らされ、うっすらと濡れて宝石のように輝いている。華奢だが、肉付きのいい肢体の大半を露出した彼女は、黄色の淡い光に照らされても、その仄かに上気した肌がよく判る。
リュカはそんな艶めかしい彼女に思わず見とれてしまった自分を恨めしく感じた。
「ここにいることが判ると、まずいんじゃない?」
「すぐに帰るよ」
リュカはビアンカから目を逸らし、部屋の中を見回していた。
「迷うことなんかないわよリュカ。自分に正直になればいいだけ」
「だから、その自分が見えないんだ。太守に言われてから、ずっと悩んでいる」
「ルドマンさんに・・・ああ」
彼女が弱々しく息をつく。
「ビアンカ、君は本当にそれでいいのか? ・・・・・・僕は君やフローラさんを試すようなことはしたくない」
リュカが思わず彼女を見て問いつめる。彼女は瞼を閉じて、口元に寂しそうな微笑みを浮かべながら小さく首を横に振った。
――――ルドマンさんに言われて、私もフローラさんも考えたわ。
そして、出した答えが・・・リュカ、あなたにすべてを任せるって。
明日、私とフローラさんは大広間に並んで、あなたが私たちのどちらかを花嫁に選ぶということ。
ルドマンさんが決めた事じゃないの。私たちでそうして欲しいって、ルドマンさんに頼んだ事よ。
ビアンカもフローラも、先晩語り合い、ともにリュカが好きである気持ちに変わりないことを確認し合った。
どちらかが身を引くのでは、きっと後悔することになるし、後味も悪くなると考えたからだ。
ならば、リュカ自身に任せてみよう。彼が選んでくれれば、後腐れもない。
そう、二人の美少女は割り切っていた。と、言うか、二人とも本気でリュカを愛しているからこそ、出せた答えなのかも知れない。
リュカとしても、そうなると生半可な気持ちのまま翌日を迎えるわけにはいかなかった。
いわば、方角が分からない大砂漠のど真ん中に立たされた心境。どこを目指して歩めばいいのだろう。一時的な感情で進めば、後戻りの出来ない永久の迷路となるかも知れない。
でも、彼自身、それでも進まねばならない道。
本当の自分の心に問い質し、自分自身を信じて決めなければならない。
道標は、太陽のようなビアンカか、夜に皓然と輝く月の如きフローラか。
「ねえリュカ?」
考え込む表情のリュカを覗き込むように微笑んだ瞳を近づけるビアンカ。驚いて反射的に顔をそらすリュカ。
「私、変わった?」
不意な言葉にきょとんとするリュカ。
「変わった・・・・・・わよね・・・」
そう漏らして視線を逸らし、寂しげな色に変わる瞳。
「あの頃とは違う・・・。あなたも、私も・・・変わったわよね・・・」
リュカには彼女の言葉が深く胸に突き刺さる思いがしていた。
そう、二人は変わった。あの頃、まだ自分が父パパスの手に引かれて世界を旅していた、幼い頃。やんちゃでお転婆だった、ビアンカ。
十年という歳月は、多感で純粋な子供にとっては、はるかに長い、あまりにも長すぎる時間だった。
右も左も判らず、ただ父に手を引かれ旅を共にし、二歳年上の少女に振り回された、頼りなげな少年は、今や善心のモンスターを従える頼もしく、凛々しい青年に成長していた。
男勝りの少女は、あの頃とは違い、健気で、気は強いままだがどこか守ってあげたくなるような、美しい女性になっていた。
二人とも自覚はしていないだろう。しかし、互いにそれを気づいたのは、再会した瞬間だった。二人の脳裏に過ぎったのは、十年前の、ありのままの少年と少女だった。
「変わってないよ。君は、あの頃のままだ・・・・・・」
リュカが彼女の金色の髪にそっと触れる。
そう思いたい。そう、信じたい気持ちで、現実を押さえ込もうとしても、天に唾するにも等しいことだった。
月日を重ねるごとに、自分たちでも気づかないうちに、何かを忘れてゆき、失くしていっているのかも知れない。思い出す。だがそれは、美化された、遠き日の思い出としてのみ脳裏によみがえる、ひとときの情景。
「ビアンカ・・・・・・」
何も言わない彼女の肩をそっと抱きよせるリュカ。洗いたての髪の香りが仄かに鼻腔をくすぐる。
彼の胸に額を当て、瞼をそっと伏せる。小刻みに震えるか細い肩。無邪気に抱きあい、ふざけ合っていたあの頃。
今、同じように彼女の背中を思い切り抱きしめようとしても、出来ない。
彼女は、そっとリュカの胸を押して身体を離す。寂しげに微笑んだ瞳で、真っ直ぐ彼の瞳を見つめる。
「幸せになって・・・・・・リュカ」
その言葉に、揺れる灯りに輝く瞳に浮かぶ宝珠に、彼女の想いがすべて凝縮されていた。そう、リュカは何も言えない。外では遠雷の轟きが静寂を破りつつあった。
「雨が降るね・・・雷の音、聞こえる・・・」
彼女が窓の方を向く。
「もう休まないと。明日、大変よ」
「・・・・・・ああ」
フォローも、慰めの言葉さえ思いつかないリュカ。
彼女の気持ちはとうに解っていたのかも知れない。
だが、たとえ何を言うにしても、言い訳にしかならないと思った。そう、同情や憐れみの心で語っても無意味であることを、解っていた。
ゆっくりと、扉のほうに歩む。遠雷が轟きを増してくる。
「お休み・・・リュカ」
「お休み」
哀しみをたたえた瞳で見つめ合い、リュカは扉を開けた。彼女も玄関先に出、彼を見送る。何度も、彼は振り返る。そのたびに胸元で小さく手を振り、微笑む。
やがて彼の姿が帳に消えると、雨が降り出してきた。小降りから徐々に強くなって行く。
彼女は家に入ろうとせず、その場に立ちつくしていた。雨に濡れる。稲妻が遠くに発し、閃光が一瞬闇を照らす。
「リュカ・・・・・・」
雨は少女の涙を、震える声は稲妻と雨の音が隠してくれていた。
「リュカ・・・・・・」
何度もその名を口にするたび、止めどなく溢れてくる涙。
そして、改めて実感する。本気でリュカを愛していた、と。春の雨は強く、それでも少女を優しく包む。
「帰りたい・・・あの頃に・・・・・・帰りたいよリュカ・・・・・・」
夜の帳に彼女は叫んだ。
心からの声が、空しく吸い込まれて消える。
雨に抱かれながら、泣いた。涙涸れ、泣き疲れて眠るまで、少女はただひたすら、泣き続けていた。
昨夜の雷雨が嘘のように、その日は素晴らしく晴れ渡った。
リュカは清々しい表情でルドマン邸に向かい、更衣室でルドマンが仕立ててくれた衣装に着替えた。いくら何でも旅のぼろぼろの衣装で式に臨むことは出来ない。
裾の長い漆黒の宮廷服に金糸の帯。
宝石の剣を佩き、さんばら髪は専属の床屋によって丁寧に洗われて光沢のある黒髪に変貌し、後ろに束ねられている。
ただでさえ凛々しい容貌が、さらに磨きがかかり美しいほどである。完成した姿を見て、使用人達も思わず感嘆の声を上げる。
「太守が大広間にてお待ちです」
使用人に先導されてリュカはゆっくりと広間に向かった。不思議なほど、落ち着いている。
「失礼仕ります」
使用人が広間の扉を開く。リュカはゆっくりと進む。上座の壇上にルドマンは正装で座していた。リュカの姿を見て思わず声を失う。
「何と・・・・・・いやはや、変わるものだな」
王族にも劣らない偉容たたえる彼の姿に、ルドマンは一瞬見とれてしまった。
「リュカ君、心は決まったかね」
「はい。もはや、心に一点の曇りもありません」
ルドマンの問いに、リュカが毅然と答える。
「そうか。ならば二人をここへ呼ぼう」
ルドマンが使用人に目を配ると、使用人は拝礼し、奥の扉に向かう。
左側と右側の扉が開き、少しの間の後、着飾った二つの人影がゆっくりと歩んできた。左からフローラ、右からビアンカ。二人の美少女の表情は緊張のため、やや硬い。俯いたまま、二人はリュカの前に並び立った。
「さあ、時は来た。リュカ君、おのが伴侶となすべき女性の前に立つのだ」
「はっ」
リュカは三度ほど深呼吸をした。そして、右足を前に出す。
戛・・・戛・・・本当にゆっくりと、リュカは意中の女性に向かう。
――――迷わなかったと言えば、嘘になるけど、僕は僕なりに深く考えた。
何度も何度も、自分の心に問いかけた。
そして、ようやく出した答えは、深く考えないということだった。
そう、今の自分に正直になればいい。
ありのままの想いを表に出して行けばいい。
昨日までの悩みが、まるで嘘みたいに心が清々しい。
後悔?
そう。
昨日までの僕だったら、きっと後悔しただろうけど
自分の選んだ道を進めば、後悔なんてしないさ
だから僕は・・・・・・
靴音が止まる。そして跪き、リュカは顔を上げ、見つめた。
そして、ゆっくりと、力強く告げる。
――――僕の、妻になって下さいますか――――
8年後、春――――
リュカとその家族は、懐かしい山奥の村へとやって来た。
「元気でいるかな」
「本当に・・・・・・久しく会っていませんでしたからね」
リュカの傍らには幼い子供二人。青い髪をした、双子の兄妹。
「ねえお父さん、誰に会うの?」
天空四防具を身につけた双子の兄が、興味津々と父の袖を取る。
「お父さんの幼なじみに会いに来たんだよ、レック」
「あれ? お父さんの昔の恋人じゃなかった?」
妹がにやりと笑いながら父を見上げる。
「こーらっ。レミ、茶化すんじゃありませんよ」
「はーい、お母さん」
レミが母の腕に絡みつく。
「レック、レミ。あそこに見える高い家がお父さんの幼なじみのお家だ」
リュカの言葉に、双子の子供達は純粋な瞳を輝かせた。
「ホントっ!?」
「そうだっ! ねえレック、競争しようよ。どっちが先にお父さんの幼なじみさん見られるか」
「ようし、望むところだ」
レックとレミは無邪気にはしゃぎながら駆け出した。
微笑ましげに自分たちの子供を見る父リュカ、そして母フローラ。
「フローラ」
ふと、リュカが口を開く。
「はい・・・」
「すまなかった」
「えっ?」
「僕と結婚したばかりに、この8年、君にはつらい目にばかり遭わせてしまって」
「そんなことありませんっ。私、とっても幸せです」
毅然と言うフローラ。
――――あの時、僕は正直、迷った。
でも、自分の心に素直になって、君を選んだ。
君を守り、幸せにするって誓った。
でも・・・守るどころか、君は生まれたばかりのレックとレミを抱き上げる間もなく、むざむざ敵にさらわれ、8年もの間ずっと苦しんできた。僕の不甲斐なさのせいだ。
俯くリュカ。フローラはそっと夫に寄り添い、腕を絡める。
――――過去を振り返るなんて、あなたらしくないですわ。
・・・私、結婚式の次の日、旅立ちに反対するお父様の前で言ったじゃありませんか。
――――たとえどんなことが起きたとしても、私は夫について行きます――――って。
「フローラ・・・」
「私、本当のこと言うと、まだあなたのことよく知らないんです。・・・でも、あなたのことを、知れば知るほど、もっと・・・もっと好きになれそうで・・・。なんて言うのか・・・すごくわくわくするの。まるで、初恋のような気持ち。初恋の人とずっと一緒にいられるなんて、すごく幸せですわ」
リュカは微笑みながら妻の肩を抱き寄せる。
彼も妻と同じ気持ちだった。そして二人は改めて感じていた。この人と一緒になって、本当に良かったと。
「おとうさーん、おかあさーんっ早くはやくぅー」
「はははは。今行くよ」
愛するわが子の呼び声に、若き夫婦は笑顔で見つめ合い、駆け出す。
懐かしき高床式の家の扉が開き、ビアンカは笑顔でリュカ達を迎えた。
結婚式の日、いつかまた出会えたなら、笑顔で話せるときが来るって、言ってた――――
私の恋は破れたけど、それも今は遠い思い出――――悲しくなんかない
それぞれの道――――自分が選んだ道だから、後悔なんてしない
私は自分の幸せをみつけるために、歩きつづけてるわ――――
だからリュカ、あなたも歩きつづけていて欲しいの――――
多分、私はそんなひたむきなあなたが好きだったから――――
リュカとその家族たちが、大魔王ミルドラースを倒し、世界に平和を取り戻したのは、それから間もない日のことであった・・・・・・。