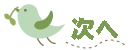|
|
|
| 大同元年(806)創建。現在の様式は、相良20代藩主長毎(ながつね)により、慶長14年(1609)から18年(1613)にかけ造営されたもの。全体の構造は鎌倉時代の様式ですが、手法は安土桃山時代の典型的な特徴をもっています。本殿、廊、幣殿、拝殿及び楼門は国指定重要文化財です。 |

|
|
楼門の軒四隅の隅木と尾捶の間に、あ・うんの相を対に彫り込んだ面が付けられています。鬼面といわれ「喜・怒・哀・楽」を表現しているとも伝えられています。これは人吉様式と呼ばれるもので、木造建築ではここ「青井阿蘇神社」のみに残っています。 |

|
|
|

|
|
五木村生まれの緋牡丹お龍が背中に入れた刺青。このモデルになったのが幣殿の牡丹の彫刻とされ、映画の撮影に使用されたことも |

|
| 廊の柱には「あ・うん」の形相をした龍の彫刻が取り付けられ、向かって右が剣を巻き込み、左が鐘を巻き込んでいます |

|
|
青井さんのまつり「おくんち」毎年10月9日に神輿は楼門を出て街を神幸する。相良700年の城下町にチリンチリンと鐘の音が響く・・・神輿、神馬、獅子、稚児などの時代絵巻が市内を練り歩く
(文:青井阿蘇神社でいただいたパンプレットより引用)
|
| Vol.1 青井神社 | Vol.2 永国寺(幽霊寺) 駅前からくり時計 |